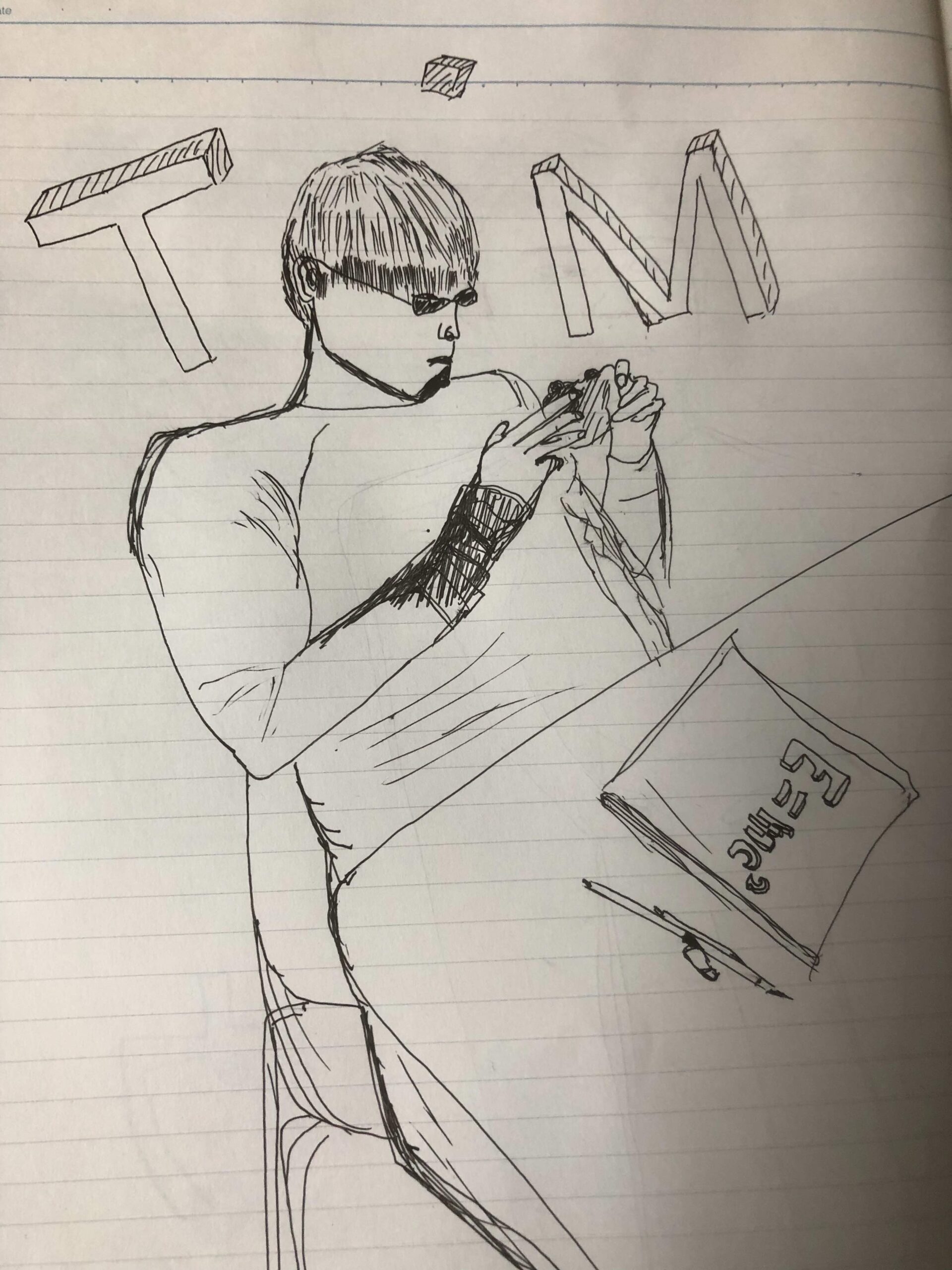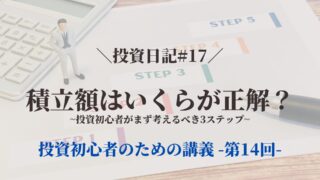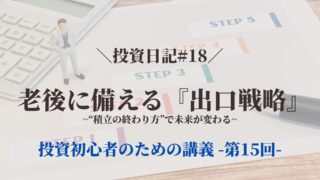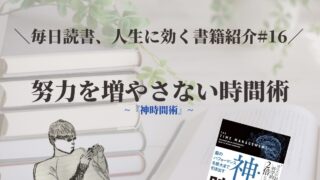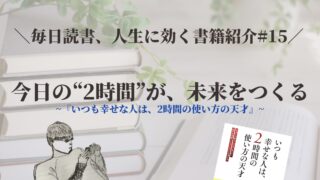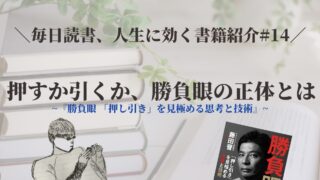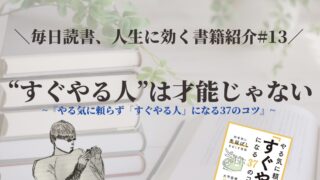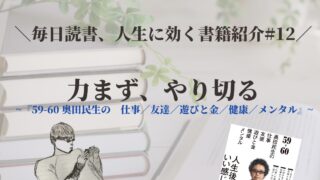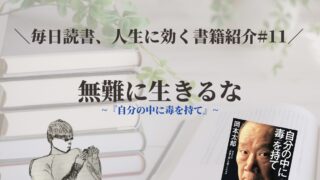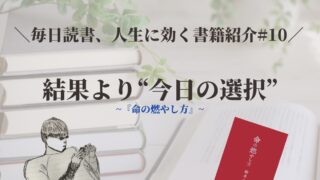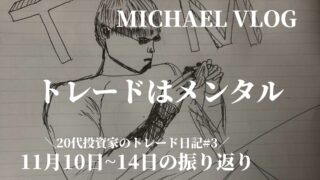#8|毎日読書、人生に効く書籍紹介『愛とためらいの哲学』~「愛されたい」を手放し、本当の愛を選び直す~
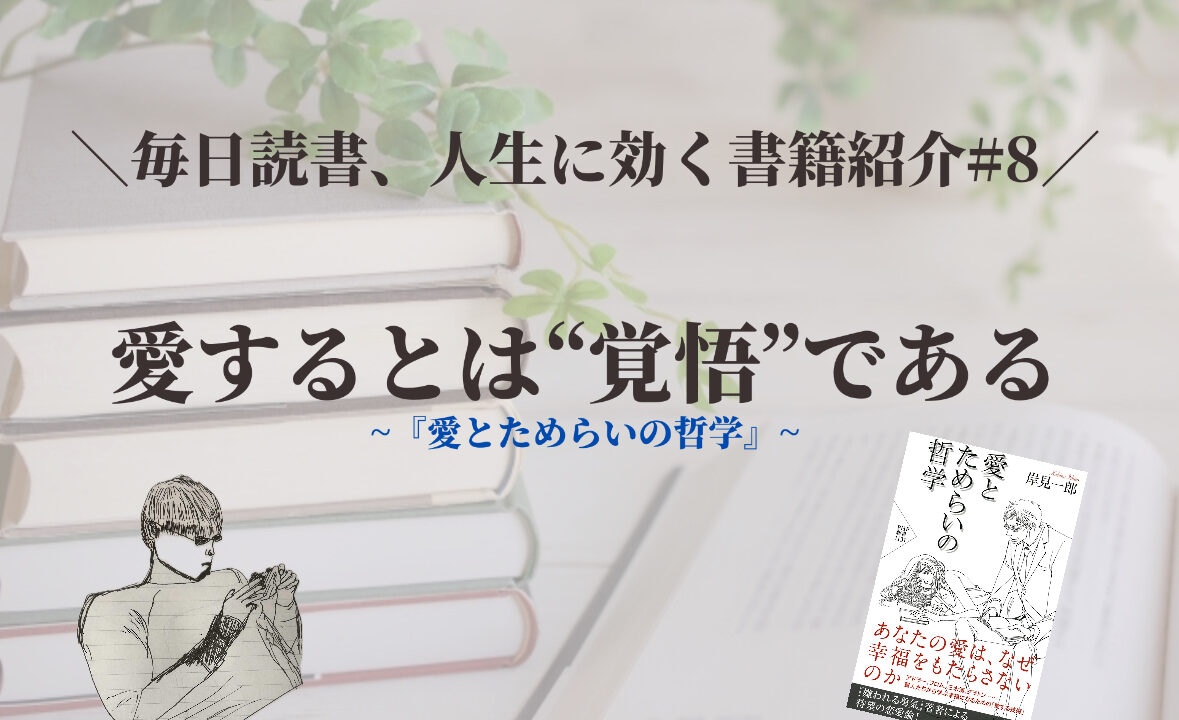
📘 この企画について
「毎日読書、人生に効く書籍紹介」は、ストイックに毎日一冊、本気で選んだ“人生に効く本”を紹介する連載企画です。
仕事・習慣・副業・自己成長に効く一冊を、実践的な視点で深掘りしています。
“愛されたい”より、“愛する”という選択を。
こんにちは!
どうも、マイケルです!
今回紹介するのは、哲学者・岸見一郎さんによる『愛とためらいの哲学』。
この本のタイトルに「愛」と「ためらい」、そして「哲学」という3つのワードが並んでいる時点で、普通の恋愛本とは一線を画していることがわかります。
- 「愛とは何か?」
- 「どうすれば人を愛せるのか?」
- 「そもそも、“愛する”とはどういう行為なのか?」
これらの問いに真正面から向き合い、アドラー心理学の背景を踏まえながら、人間関係全般、特に恋愛や結婚といった“親密な関係性”について深く切り込んでいく本書は、ただの恋愛指南書でもなければ、自己啓発書でもありません。
哲学者としての思考と、臨床の現場で人と向き合ってきた経験が融合し、まさに「人生の軸としての愛」を学ぶ書になっています。
本記事では、全8章+気づきのコーナーで『愛とためらいの哲学』を徹底的に読み解きます。
今、“誰かとの関係性”に悩んでいる人へ。
この一冊が、人生の視界を一変させてくれるかもしれません。
- 人を「愛すること」に自信がない人 → 愛とは“才能”ではなく“選び続ける哲学”であることに気づけます。
- 恋人・夫婦関係で悩んでいる人 → 価値観のズレ・依存・不安など、パートナーシップの核心に効きます。
- 「自立」と「愛」のあいだで揺れている人 → ひとりで立つ力と、誰かと生きる力の両立を学べます。
- 恋愛や結婚を“哲学”として捉えたい人 → 感情論ではなく、“どう生きるか”という視点から関係性を考えられます。
- アドラー心理学に関心がある人 → 『嫌われる勇気』に共感した人にとって、本書は実践的な続編ともいえます。
どれか1つでも当てはまるなら、
この本の中に、あなたの悩みを軽くするヒントがきっとあります。
(第8回の書籍はこちら)
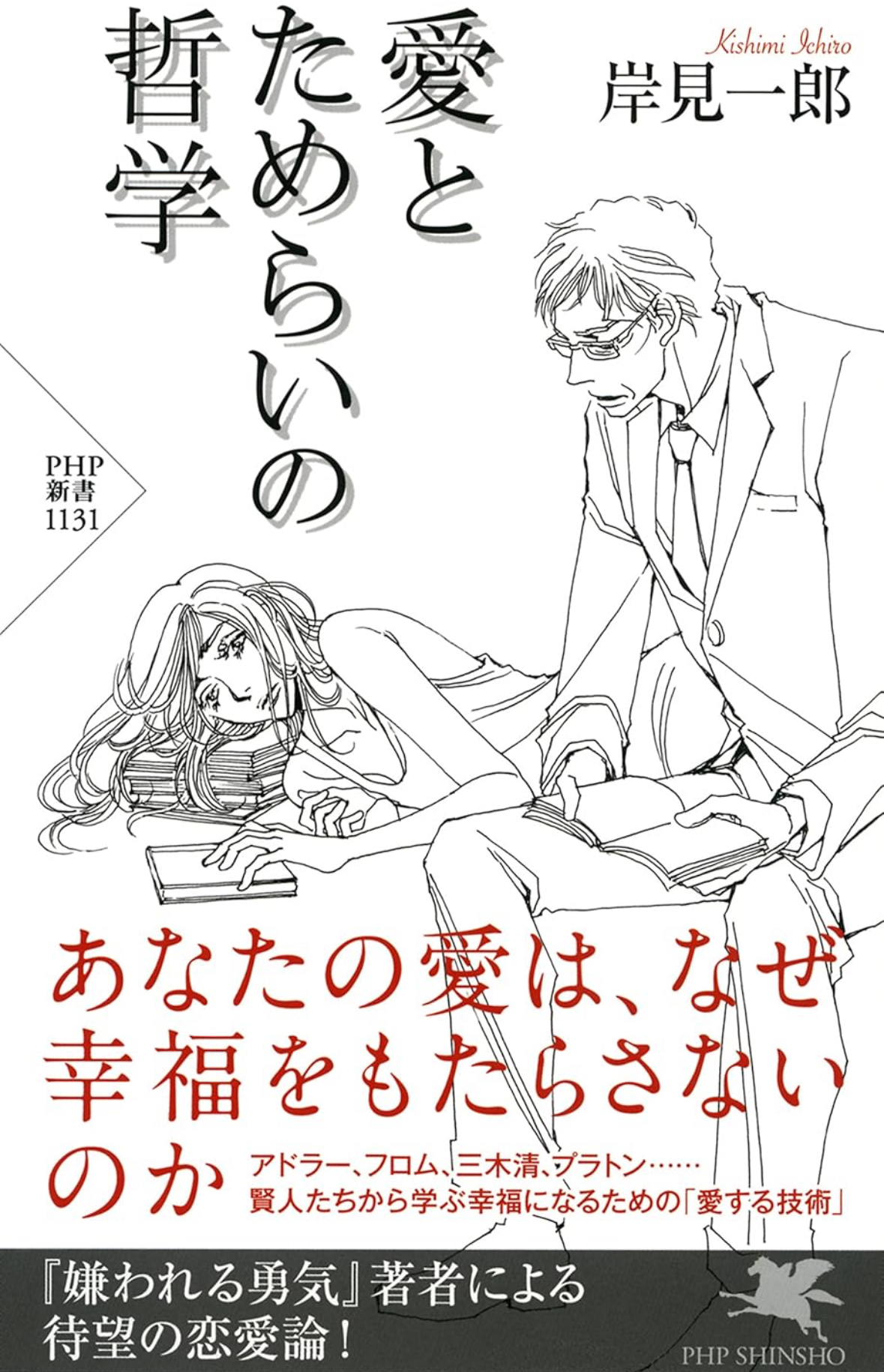
目次
第1章|「愛されたい」は“本当の愛”ではない
- 「好きな人に好かれたい」
- 「嫌われたくない」
人は誰しも、無意識のうちにこうした欲求を抱いてしまうものです。
けれども、岸見一郎さんは本書の冒頭から明言します。
「愛されたい」という欲望は、愛ではない。
これにはドキッとさせられました。
なぜなら僕自身、「どうしたら好かれるか?」を考えすぎて、自分を見失っていた時期があったからです。
- 相手の機嫌
- 相手の気持ち
- 自分の立ち位置
いつしか愛することより、「評価されること」「選ばれること」ばかりに意識が向いていました。
しかし岸見さんは、この“他者中心の愛”こそが、苦しみの原因だと言います。
つまり、「誰かに愛されたい」と思う限り、僕たちは永遠に不安を抱える存在になってしまうのです。
ではどうすればいいのか?
岸見さんが提示する答えは明快です。
愛は“与える”ものであって、“受け取る”ものではない。
この言葉が持つ重みは、実際に誰かを本気で愛した経験がある人ほど理解できるはずです。
相手がどう思っていようと、自分の中にある「その人を大切にしたい」という気持ち。
そこに見返りはない。
見返りを求め始めた瞬間、それは取引や依存に変わってしまう。
この視点こそ、愛に向き合う上で最も本質的な哲学ではないでしょうか。
また、「愛されたい」という欲求には、しばしば“承認欲求”が混ざります。
「自分は価値ある存在だ」と感じたいがために、誰かに必要とされることを求めてしまう。
でも、それは『相手を愛している』のではなく、『愛されている自分』に酔いたいだけなのかもしれません。
この章を読み終えたとき、僕の中で静かな覚悟が芽生えました。
誰かに必要とされることではなく、
誰かを“本気で必要とすること”。
それこそが、自分にとっての“愛する”という行為なのだと。
第1章|マイケルの気づき
「愛されたい」と願っていた頃は、常に不安だった。
「愛そう」と決めたとき、心が静かになった。
第2章|ためらいは“誠実さ”の証である
- 「この人のことを好きだけど、なかなか素直になれない」
- 「もっと踏み込みたいけど、怖さが勝ってしまう」
そんなふうに、『ためらい』が心にブレーキをかけるとき、私たちはついこう考えてしまいます。
自分は臆病なんじゃないか、と。
でも岸見一郎さんは、真逆のことを語ってくれました。
「ためらいがある人ほど、愛に対して誠実である」
この言葉に、僕は救われました。
むしろ、ためらいもなく関係を築こうとする人のほうが、軽率だったり、自分の欲を優先しすぎている場合がある。
本当に相手を大切にしたいと思っている人ほど、心を開くことに慎重になる。
それは、誠実さの現れなのだと本書は教えてくれます。
僕自身、過去の恋愛で「これ以上踏み込んで嫌われたらどうしよう」と、一歩引いてしまった経験があります。
その時は「勇気がなかった」と自分を責めていました。
でも、今になって思うのです。
あの『ためらい』は、相手のことを真剣に思っていた証だったのだと。
岸見さんはこうも語ります。
「好きだからこそ、言葉を選ぶ」
「愛しているからこそ、沈黙を選ぶこともある」
つまり、『愛している=積極的に動く』とは限らないということ。
時に『立ち止まること』や『黙って見守ること』も、深い愛の形なのです。
現代はスピードと即断がもてはやされる時代です。
恋愛においても、返事の速さやLINEの頻度が「関心度」のバロメーターになってしまうことすらあります。
でも、岸見さんの言葉は、そんな風潮に一石を投じてくれます。
「すぐに答えを出さないこと」は、逃げでも無関心でもなく、相手と真剣に向き合おうとする姿勢なのです。
人と関わることは、正解のない旅路。
だからこそ、その一歩を踏み出す前に“ためらう”ことは、まぎれもなく誠実さの証。
むしろ、ためらいのない愛のほうが、危ういのかもしれません。
第2章|マイケルの気づき
勇気がないんじゃない。
大切にしたいからこそ、ためらってしまうんだ。
第3章|愛とは“共に生きる”という選択である
「あなたがいないと生きていけない」
一見ロマンチックに聞こえるこの言葉。
しかし岸見一郎さんは、こうした“溶け合うような関係”に対して明確に距離を置きます。
愛とは、一体化ではなく“共に生きる”ことである。
恋愛や結婚において、僕たちはつい「ひとつになりたい」と願いがちです。
すべてを共有し、価値観も、好みも、未来のビジョンもピタリと一致する相手こそが『運命の人』だと考えてしまう。
けれど本書では、そうした幻想をやさしく壊してくれます。
愛とは、“自分”と“相手”という独立した存在が、並びながら生きていくこと。
お互いの違いを認め、尊重し、それでも共に歩むと決めること。
これこそが「本当の愛」だと岸見さんは言うのです。
この章で印象的だったのが、愛するとは「自分の人生に、相手の人生を迎え入れること」だという一節。
つまり、自己犠牲でもなく、依存でもなく、“ふたりの人生をすり合わせる努力”こそが愛の形なのです。
そのためには、自分自身の価値観をしっかり持っていることが大前提。
「相手に合わせる」だけの生き方では、自分を失い、いつか破綻する。
逆に、自分を押しつけてばかりいても、相手の存在を否定してしまう。
愛とは、互いの違いを抱えながら、“二本の足で立つことを選び続ける関係”なのです。
この考え方を知ったとき、僕の中で過去の恋愛の失敗がいくつか腑に落ちました。
相手にすべてを合わせていたときも、自分の価値観を押しつけていたときも、どちらも“独立したふたりの関係”ではなかった。
その反省から、今はこう思っています。
「どんなに愛していても、相手は“自分とは違う人間”である」
その前提に立てる人こそが、本当の意味で“愛する準備”ができているのだと。
第3章|マイケルの気づき
一体にならなくていい。
隣で、同じ景色を見つづけられる関係があれば、それでいい。
第4章|“ひとりで生きる力”が、“ふたりで生きる力”をつくる
「この人がいないと生きていけない」
そう思えるほどの愛を、誰もが一度は夢見たことがあるかもしれません。
けれども岸見一郎さんは、あえてその理想に真っ向から異を唱えます。
真に愛することのできる人は、“ひとりでも生きていける人”である。
これを初めて読んだとき、僕の中で何かがはじけるような衝撃がありました。
今まで「誰かと一緒にいること」が幸せだと信じてきた。
でも本当は、「誰かに依存していないこと」こそ、愛の前提だったんだと気づかされたんです。
たとえば、
孤独が怖いから恋人をつくる。
寂しさを埋めるために誰かを求める。
それは“愛する”というより、“必要とする”に近い。
岸見さんは、こうした“代償的な愛”に鋭い視線を投げかけます。
つまり、心のどこかで「誰かがいなければ、自分の人生は成立しない」と感じているうちは、対等な関係は築けないのです。
自分の人生を自分で引き受ける覚悟。
ひとりで立つ強さ。
そのうえで、「あなたと一緒にいたい」と思える状態こそが、“ふたりで生きる力”の本質です。
ここで岸見さんが紹介する考え方に、「人生は誰のものか?」という問いがあります。
答えは当然、「自分のものである」。
にもかかわらず、恋愛や結婚となると、「相手の期待に応えなければ」「パートナーの言う通りにしないと」と、自分の人生を明け渡してしまう人が多い。
これは“愛”ではなく“服従”に近いものです。
本書は、こうした思考に対して「NO」と言ってくれる一冊です。
僕たちは、誰かの所有物になるために愛するのではない。
自分の人生に誇りを持ったまま、誰かと並んで歩くために愛するのです。
第4章|マイケルの気づき
誰かに依存しない強さが、
誰かと共に生きる優しさを育ててくれる。
第5章|「見せたくない自分」こそ、見せる価値がある
あなたは、どこまで自分を“さらけ出せる”だろうか?
好きな人に、自分の弱さや欠点をそのまま見せることに、抵抗を感じたことはないだろうか?
岸見一郎さんはこの章で、こう語ります。
愛とは、「見せたくない自分」を見せる勇気である。
人は誰でも、「こう見られたい自分」を無意識のうちに演じています。
特に恋愛の初期段階では、好かれたい一心で“完璧な自分”を見せようとしてしまう。
- 弱音を吐かない
- 余裕のあるふりをする
- 過去の失敗を隠す
でも、それを続ける限り、“本当の関係”は築けません。
なぜなら、そこにいるのは「演じた自分」だから。
相手が好きになっているのは“虚像”であり、あなたのすべてではない。
岸見さんは、こう問いかけます。
「自分のすべてを見せられない関係に、果たして本当の愛は存在するのか?」
この問いはとても深く、僕の心に残りました。
僕たちは「愛されること」ばかりに意識が向きすぎて、「見せる勇気」を忘れがちです。
でも本当は、弱さを共有し合える関係こそが、安心で、信頼に満ちた本物のつながりなんです。
僕自身も、過去に「ダメな部分を見せたら嫌われるかもしれない」と怯えて、自分の内面をさらけ出せなかったことがあります。
でも、その関係は結局、どこか浅く、安心できるものではありませんでした。
一方で、自分のダメさも、過去の失敗も、未熟さもさらけ出して受け入れてもらえたとき、
「この人とは、本当に深く繋がれた」と感じた瞬間がありました。
岸見さんはそれを「愛の深まり」と表現します。
見せたくない自分を見せることで、初めて“信頼”という土台が育つのだと。
第5章|マイケルの気づき
完璧な自分じゃなくていい。
見せられる弱さこそ、本当の強さだ。
第6章|結婚とは“価値観の違い”を楽しむ旅である
「結婚するなら価値観が合う人がいい」
これは、誰もが一度は口にしたことのある言葉かもしれません。
でも、岸見一郎さんはあえて次のように言います。
結婚とは、価値観が違う人と共に生きる“訓練”の場である。
ここに、本書の核心があります。
恋愛と違って、結婚は“日常の連続”。
朝起きて、ごはんを食べて、仕事をして、家事をして、寝る
その繰り返しのなかで、相手とどう向き合っていくかが試される関係です。
その中で必ずぶつかるのが、『価値観の違い』。
- 食べ物の好み
- 片づけのルール
- お金の使い方
- 休日の過ごし方
どんなに似た者同士に見えても、細部を見ればズレはある。
そこで重要なのは、「違うから無理」と線を引くのではなく、「違うからこそ学べる」という姿勢を持てるかどうか。
岸見さんはこう言います。
相手と価値観が違うとき、自分の生き方を問い直すチャンスになる。
つまり、価値観の違いとは“衝突”ではなく、“対話”の入り口。
相手を否定するのではなく
相手の視点を借りて
自分を見直す良い機会なのです。
結婚生活とは、
相手に自分の正しさを押しつける場ではなく、
“違いの中に意味を見出す共同作業”だ
そう岸見さんは語ります。
これは非常に成熟した愛のあり方です。
僕たちはつい、「自分と同じ価値観の人なら、うまくやっていける」と思いがちですが、
本当は、違う価値観にどう向き合えるかのほうが、関係の深さを決めているのです。
僕自身、「自分に似ている人」との関係が長続きしなかった経験があります。
逆に、「正反対の価値観を持つ人」とのほうが、対話と発見があり、関係が育っていったということもありました。
結婚とは、“同じになる”ことではなく、“違うまま一緒にいる”ための訓練。
そこにこそ、愛の成熟があるのだと実感しています。
第6章|マイケルの気づき
わかり合えるから一緒にいるんじゃない。
わかり合おうとする姿勢こそ、愛のかたちだ。
第7章|関係を深めるのは“正しさ”ではなく“理解”
人と意見が食い違ったとき、あなたは何を優先するだろうか?
「自分の正しさを伝えたい」と思うだろうか。
それとも、
「相手の気持ちを理解したい」と思うだろうか。
岸見一郎さんは本章でこう語っています。
人間関係において、“正しさ”の押しつけほど関係を壊すものはない。
これは恋人同士だけでなく、夫婦・親子・友人関係にも共通する深い真理です。
どんなに理論的に正しかったとしても、それが「相手を屈服させるための武器」になった瞬間、関係性は対等ではなくなります。
そして、対等でない関係には、健全な“愛”は存在しません。
本当に必要なのは
正しさの主張ではなく、「相手の感じ方」を受け止める姿勢。
岸見さんはこれを「共感的理解」と呼びます。
たとえば
パートナーとケンカしたときに
「でも俺は正しいことを言ってる」ではなく、
「君はどうしてそう感じたんだろう?」
と問いかける勇気があるかどうか。
その姿勢こそが、愛を継続させる土台になります。
この章を読んで僕は、自分の過去の言動をたくさん思い出しました。
- 正論を振りかざして、相手を黙らせたこと。
- 「言い負かした」という自己満足だけが残って、関係はどこか冷えていったこと。
でも、どんなに正しくても、相手が“傷ついた”と感じたなら、その感情こそが事実なのです。
愛する人との関係で大切なのは、「どっちが正しいか」ではなく、「どう一緒に前へ進めるか」。
この視点を持てるようになるだけで、コミュニケーションは劇的に変わります。
正しさよりも、理解。
説得よりも、共感。
“勝つこと”ではなく、“寄り添うこと”。
岸見さんの言葉は、ただの技術論ではありません。
人と向き合うときの“あり方そのもの”を教えてくれる哲学です。
第7章|マイケルの気づき
正しさが人を変えることはない。
変えるのは、理解しようとする“姿勢”だけだ。
第8章|愛するとは、“相手の人生を生きること”
本書のクライマックスにあたるこの章で、岸見一郎さんは「愛とは何か?」という問いに対して、明確な答えを提示します。
愛するとは、“相手の人生を、自分の人生として引き受けること”である。
この一文に、愛というものの本質がすべて凝縮されています。
つまり
愛とは「好き」という感情のことでも、「一緒にいて楽しい」という共感でもなく、
「この人の人生を、自分ごととして共に歩んでいく」という“決断”なのです。
この視点に立てたとき、僕たちの中にあった“愛のイメージ”は大きく塗り替えられます。
- 趣味が合うから
- 居心地がいいから
- 一緒にいると安心するから
それだけでは“共存”に過ぎないんです。
「この人の困難も、悲しみも、過去も、未来も──自分が引き受けたい」
そう思える覚悟こそが、“愛する”という行為の中身なのです。
岸見さんはこうも語っています。
相手の存在を“自分の人生の中心に据える”ことで、愛は形を持つ。
その中心には、自己犠牲でも、依存でもない、“主体的な選択”があります。
つまり
「あなたと共に生きる」という選択を、毎日繰り返すこと。
それが“愛”という言葉の正体なのだと気づかされます。
恋愛は、時に勢いで始まります。
でも、長く続く愛には、意志と選択が必要です。
「今日もこの人と向き合い続ける」と決めること。
その選択を積み重ねていく先にこそ、深い信頼と安心が生まれる。
僕たちは、“偶然の出会い”で人と繋がるけれど、
“継続する愛”は、毎日の小さな決断の積み重ねでつくられていく。
愛とは、誰かと生きることを、
「自分の人生の一部として引き受ける」こと。
その覚悟を持てるとき、はじめて“本物の愛”が、人生のなかに根づいていくのかもしれません。
第8章|マイケルの気づき
愛するとは、想うことではない。
「共に生きる」と、毎日決め直すことだ。
まとめ|愛とは、“選び続ける”という生き方そのもの
岸見一郎さんの『愛とためらいの哲学』は、「愛するとはどういうことか?」という誰もが抱える根源的な問いに対して、極めて静かで深い“哲学的な答え”を与えてくれる一冊でした。
恋愛も
結婚も
友情も
「人と共に生きる」という営みの中で、僕たちは時に迷い、ためらい、不安になります。
でも本書は、そのすべての“揺らぎ”を肯定しながら、こう語ります。
それでも、愛するということは、“相手の人生を自分の人生として引き受けること”。
これは、感情の浮き沈みに支配される「好き・嫌い」の話ではありません。
むしろ、自分の意志で選び取っていく、“生き方の問題”なのです。
本書を通じて僕が学んだこと
- 「愛されたい」ではなく、「愛する」ことを選ぶ
- ためらいは、誠実であろうとする人の証
- 一体化ではなく、“並んで歩く”ことが愛の形
- ひとりで立てる人こそ、愛に向き合える
- 弱さを見せることが、つながりを生む
- 結婚とは、違いを楽しむ“共同の旅”
- 正しさよりも、理解しようとする姿勢
- 愛とは、選び続けるという“生き方”
どれも派手な言葉ではありません。
だけど、どこまでも“本質的”で、“普遍的”なメッセージです。
僕は本書を読んで、愛することへの不安が少しだけ小さくなりました。
そして、「それでも人と向き合い続けたい」と思えるようになりました。
人を信じること。
自分を信じること。
そして、誰かと共に生きること。
そのすべては、“選び続ける勇気”から始まります。
愛とは、特別なことじゃない。
毎日を、誰かと“選び直す”ことだ。
最後まで読んでいただきありがとうございました!
皆さんの人生に効く本を、これからも一冊ずつ丁寧に届けていきます。
次回の「書評日記」もお楽しみに!!!
📚 書評日記シリーズ|人生に効く本だけ、集めました
読書は、知識だけじゃなく“生き方”も整えてくれる。
このシリーズでは、僕自身が読んで心動かされた本、明日からの行動が変わった本だけを、厳選して紹介しています。
今の気分に合いそうな一冊があれば、ぜひ読んでみてください👇
- #1『世界の一流は「休日」に何をしているのか』| 休むとは、整えること
- #2『人生をガラリと変える「帰宅後ルーティン」』| 疲れた夜に未来を仕込め
- #3『明るい人の科学』| “明るさ”は才能じゃない
- #4『STOIC 人生の教科書ストイシズム』| 外に振り回されない生き方
- #5『一流の人に学ぶ心の磨き方』|一流の人は、心を磨き続ける
- #6『悩まない人の考え方』|思考を整えれば、心は軽くなる
- #7『エッセンシャル思考』|本当に大事なことをやれ
- #8『愛とためらいの哲学』|愛するとは“覚悟”である ← 今回の記事
📖あなたの明日を変える1冊が、きっとここにある📖