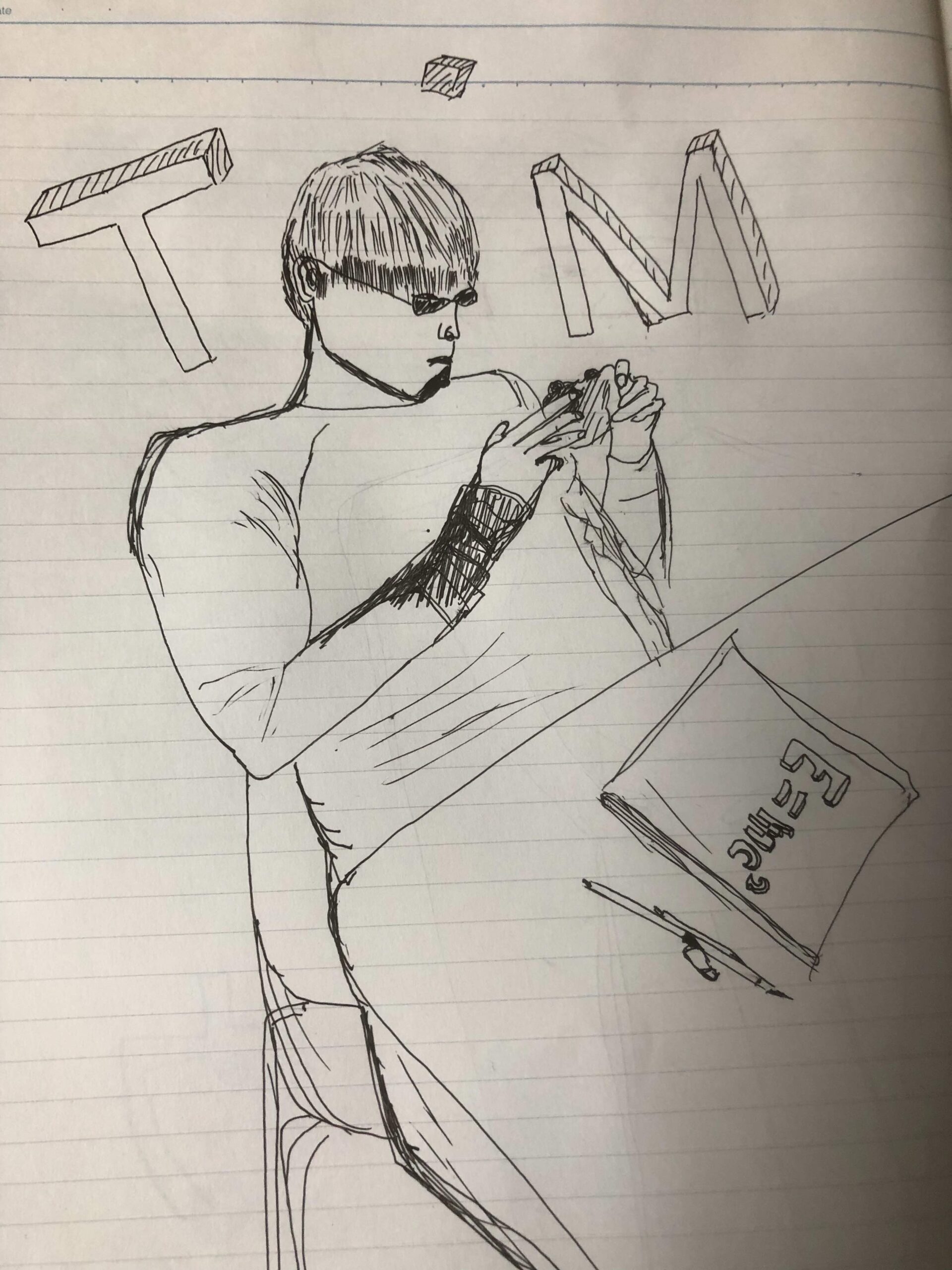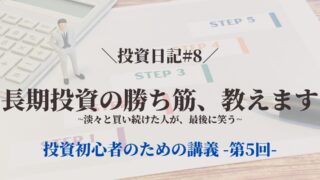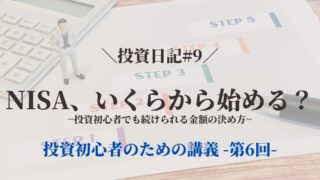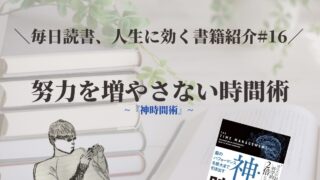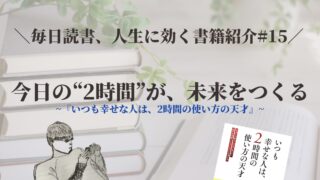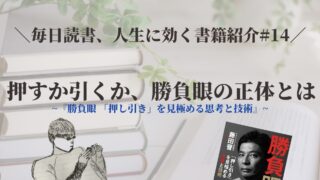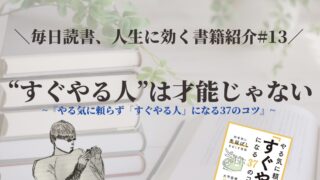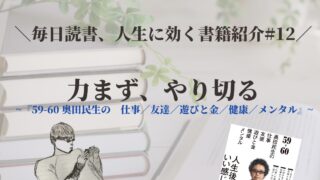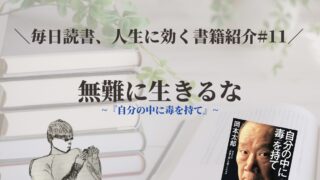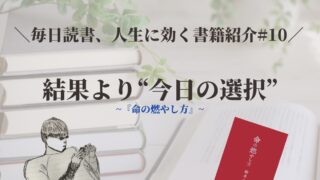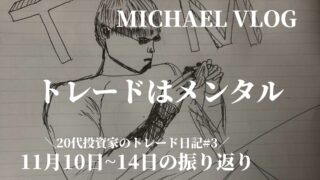#3|毎日読書、人生に効く書籍紹介『明るい人の科学』~“笑えない日”こそ、未来を変えるチャンス~
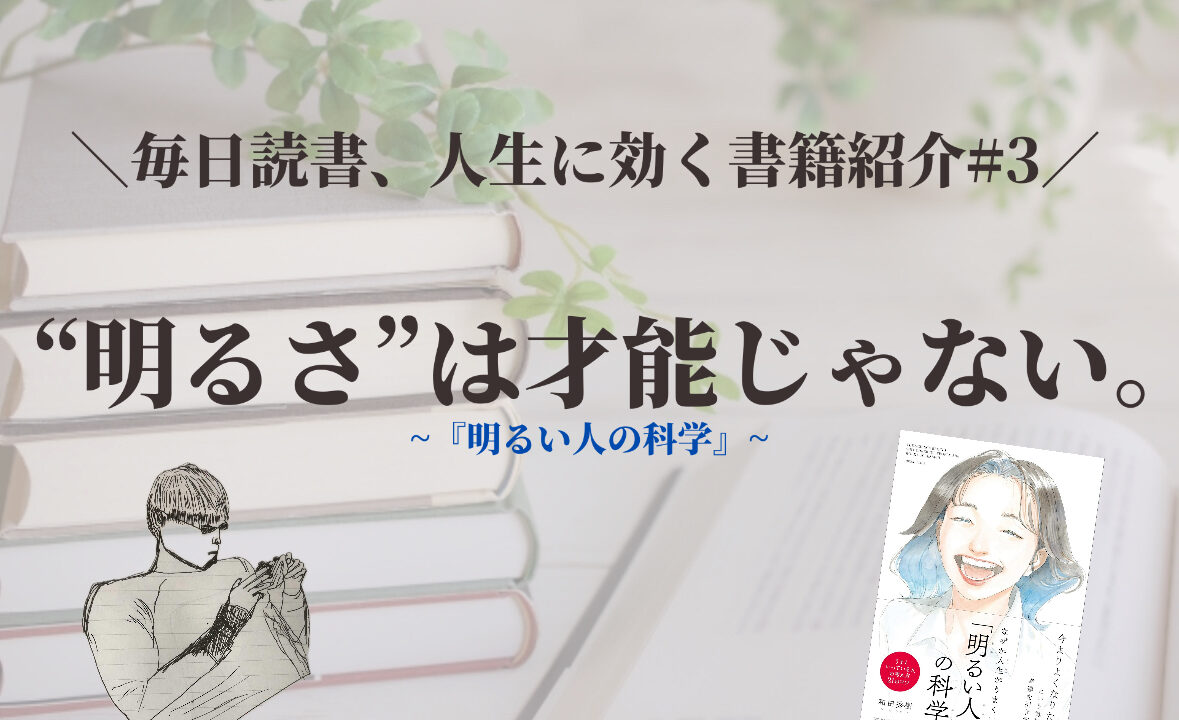
📘 この企画について
「毎日読書、人生に効く書籍紹介」は、ストイックに毎日一冊、本気で選んだ“人生に効く本”を紹介する連載企画です。
仕事・習慣・副業・自己成長に効く一冊を、実践的な視点で深掘りしています。
こんにちは!
どうも、マイケルです!
今日も“ゆるストイック”に、読書の時間を楽しんでいます。
今回ご紹介するのは、精神科医・和田秀樹さんの著書『明るい人の科学』。
「なんとなく人生がうまくいってる人」って、なぜか明るい人が多い。
でもその“明るさ”って、本当に才能なんでしょうか?
本書は、「明るさは習慣であり、科学である」というテーマのもと、
精神医学・脳科学・心理学の視点から“明るく生きる力”の正体を解き明かしてくれます。
読むたびに、「もっと軽やかに、もっと素直に生きていいんだ」と背中を押される一冊。
今回は、そんな“明るさのメカニズム”を、全10章でじっくりと深掘りしていきます。
(第3回の書籍はこちら。)
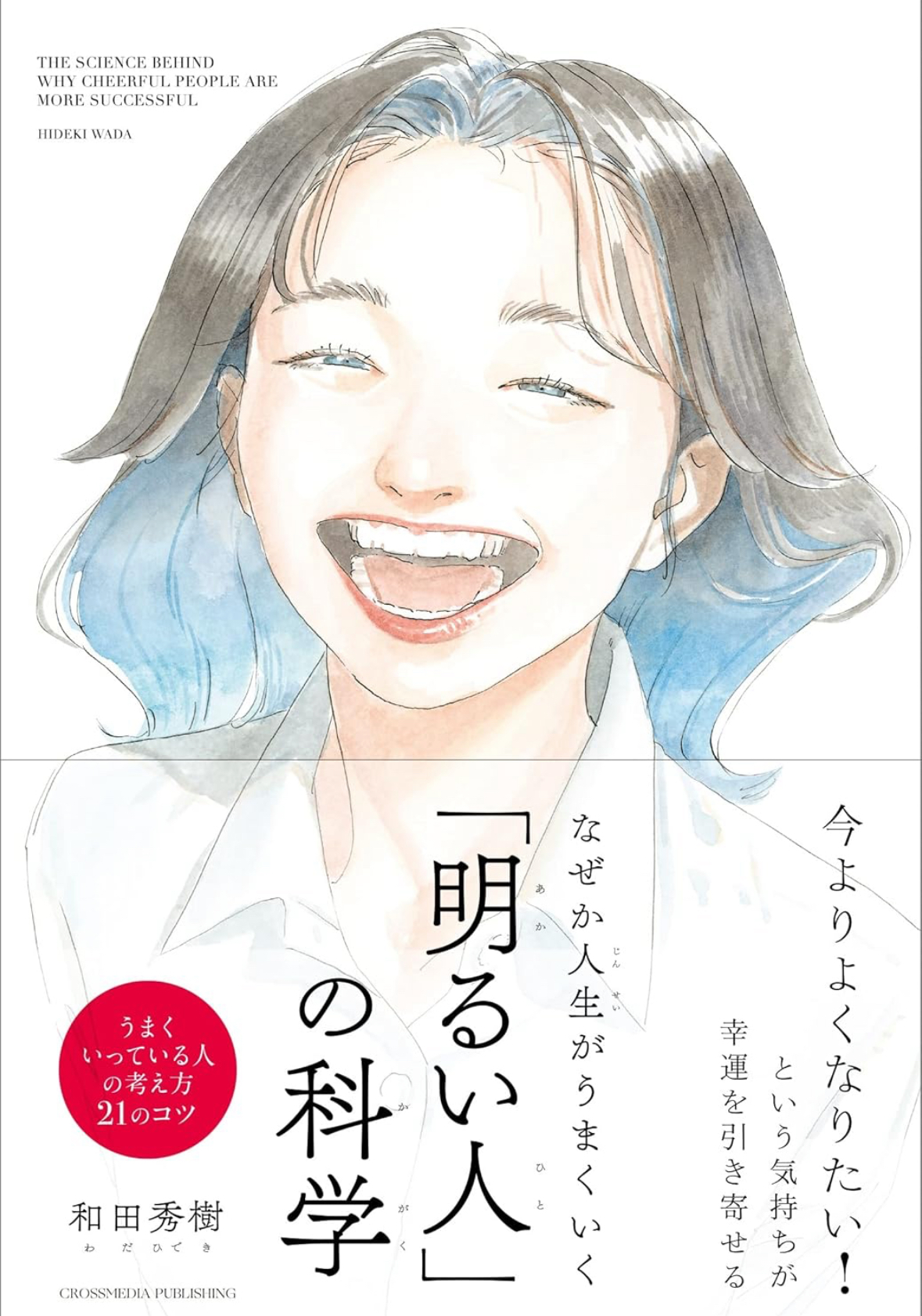
目次
第1章 明るさは才能ではない、「思考の癖」で決まる
「明るい人」と聞いて、どんな人物を思い浮かべるでしょうか?
いつも笑顔で、ポジティブな言葉を使い、人に囲まれている。
そんな“元気印”のような人は、つい「生まれつきなんだろうな」と思ってしまいがちです。
でも本書では、その前提を真っ向から否定します。
精神科医として40年以上にわたり多くの人と接してきた和田秀樹さんは、「明るさは才能ではなく、思考の“癖”によってつくられている」と断言します。
僕たちは、毎日さまざまな出来事に直面します。
それをどう解釈するか。ここに明るさと暗さの分岐点があるのです。
出来事は同じでも、解釈が違うだけ
たとえば、仕事でミスをしたとしましょう。
- 明るい人:「いい経験になった。次はうまくやろう」
- 暗くなる人:「自分はやっぱりダメだ。みんなに嫌われたに違いない」
このように、出来事自体は同じでも、受け取り方・考え方次第で、その後の気分も行動もまったく変わってしまいます。
本書では、こうした思考の違いを「認知のクセ」と呼び、そこに明るさの本質があると語ります。
つまり、明るく生きるために必要なのは
「物事をポジティブにとらえる訓練」
言い換えれば、“考えグセ”を意識的に変えていくことで、誰でも「明るい人」になれるのです。
明るさは「選択」である
さらに本書では、「明るさは日々の選択の積み重ね」とも述べています。
- 朝起きて、どんな表情をするか。
- 人と話すとき、どんな言葉を選ぶか。
- 落ち込んだとき、どんな風に切り替えるか。
こうした日々の小さな判断の積み重ねが、いつしか「その人らしさ」をつくっていく。
つまり、「明るい人になる」とは、何か特別な技術を持つことではなく、“明るさを選び取り続ける姿勢”なのです。
マイケルの気づきコーナー
「明るくなる」は、才能じゃない。
毎日の“考えグセ”が、君のキャラを決めている。
自分を変えたいなら、まず「ものの見方」を疑ってみよう。
第2章 “感情の悪循環”から抜け出す3つのヒント
明るくなりたいと思っても、実際にはネガティブな感情に引きずられる日もあります。
- 不安
- 落ち込み
- 自己嫌悪
- 焦り
こうした負の感情が次々に連鎖してしまうと、「明るくあろう」とする努力すら無力に感じてしまうものです。
本章では、そんな『感情の悪循環』を断ち切るための具体的なヒントが3つ紹介されています。
それぞれのポイントを見ていきましょう。
1. 考えすぎ(反芻思考)を止める
まず最初に挙げられるのが、「反芻(はんすう)思考」。
あれこれとネガティブなことを何度も何度も頭の中で反復してしまう状態です。
たとえば、
- 「なんであんなこと言っちゃったんだろう」
- 「もっとうまくできたはずなのに…」
- 「あの人、怒ってるかもしれない」
こうした思考を何時間も繰り返してしまうことは、誰にでもありますよね。
和田さんはこれを『脳のバグ』のようなものと説明します。
反芻思考は、過去のミスを「分析」しているようで、実は「自己攻撃」になっていることが多い。
そんなときこそ、あえて“思考を止める勇気”が必要です。
ポイントは「声に出す」「動く」「体を使う」。
思考が止まらないときこそ、言葉と行動の力を使ってリセットしましょう。
2. 決めつけ思考を疑う
次に問題になるのが、「決めつけ」。
自分に対して、あるいは他人に対して、「どうせ○○だ」というレッテルを貼ってしまう癖です。
- 「どうせ自分は嫌われている」
- 「あの人は自分のことをバカにしている」
- 「結局うまくいかないに決まってる」
こうした決めつけは、感情の悪化を加速させる最強の燃料です。
そしてその多くは、事実ではなく“思い込み”にすぎないことがほとんど。
和田さんは、「その思い込み、根拠ある?」と問いかける力を鍛えようと述べています。
決めつけを疑うだけで、心の自由度は一気に広がります。
3. 不安は「確率」でとらえる
3つ目のヒントは、「不安を確率で見る」ということ。
人間は、まだ起きていない未来に対して「最悪のケース」を想像しがちです。
- 「このプレゼン、失敗したらどうしよう」
- 「もしかして会社をクビになるかも…」
でも、実際にそれが起きる確率って、どのくらいあるでしょう?
大抵の不安は、実際に起きる可能性が1%にも満たないのです。
そこで大事になるのが、「起きてから考えればいい」という感覚。
心配にエネルギーを使いすぎず、今やるべきことに集中する。
その切り替えが、明るさにつながっていきます。
マイケルの気づきコーナー
未来の不安は、だいたい嘘つき。
「起きてから考える力」が、感情を守ってくれる。
明るく生きるって、要するに“あんまり気にしない”ことだ。
第3章 脳は“笑顔”に引っ張られる
僕たちはよく、「楽しいから笑う」と思いがちです。
でも本書では、驚きの事実が語られます。
- 「笑うから、楽しくなる」
- 「作り笑顔でも、脳は騙される」
つまり、感情よりも先に表情を動かすことで、心が後からついてくる。
この現象は「表情フィードバック仮説」と呼ばれ、心理学の分野でも数々の研究によって裏付けられています
笑顔が脳に与える影響
笑顔をつくると、脳内でセロトニンやエンドルフィンといった『幸福ホルモン』が分泌されます。
これらの物質には、以下のような効果があります。
- 気分が安定する
- ストレスに強くなる
- 免疫力が向上する
- 不安やイライラが軽減される
驚くべきは、「本当に楽しいかどうか」は関係ないという点です。
たとえ“作り笑い”でも、脳はそれを「楽しい状況」と錯覚し、ポジティブな反応を引き起こしてくれるのです。
表情は他人にも影響する
もう一つ重要なのは、笑顔が「伝染」するということ。
人間には「ミラーニューロン」と呼ばれる仕組みがあり、相手の表情や態度を無意識に真似する性質があります。
つまり、自分が笑顔でいれば、相手も自然と笑顔になる。
逆に、自分が不機嫌なら、その空気は周囲に伝わり、場の雰囲気全体を重たくしてしまいます。
和田さんはこれを「感情の引き算ではなく、足し算で人と関わる」と表現します。
笑顔とは、言葉を使わずに相手と心を通わせる『非言語のギフト』なのです。
「笑顔習慣」は後天的に身につけられる
では、普段から笑顔が苦手な人はどうすればよいのでしょうか。
和田さんの答えはシンプルです。
「口角を上げる練習をすればいい」
最初はぎこちなくても、毎日鏡の前で3分でも練習すれば、次第に自然な笑顔が身につくようになります。
ポイントは、「無理に笑う」のではなく、「笑う準備を習慣にする」こと。
- 朝:鏡に向かってニコッとする
- 通勤中:意識して軽く口角を上げる
- 人に会う前:軽く深呼吸してから笑顔のイメージを持つ
こうした小さな積み重ねが、あなたの表情と人生を変えていくのです。
マイケルの気づきコーナー
感情は、後からついてくる。
まずは「笑ってみる」。それが、脳を味方につける第一歩。
今日の表情が、明日の運をつくる。
第4章 「明るい人」の21の思考習慣
「明るくなりたい」と思っても、性格をいきなり変えるのは難しい。
でも本書には、明るい人たちが自然にやっている“思考の習慣”が21個紹介されています。
それらはどれも、誰でも今日から取り入れられる“日常の工夫”ばかりです。
ここではその中から、特に印象に残った5つの習慣を紹介しつつ、僕自身の視点で掘り下げていきます。
1. 失敗は「データ」として扱う
明るい人は、うまくいかなかったことを“失敗”と考えません。
失敗したとしても
「うまくいかなかった方法を1つ見つけた」
と捉え、それを次の行動に活かします。
この『データ思考』を持つことで、自己否定に陥らずに前を向くことができるのです。
2. 比べるなら「過去の自分」
他人との比較は、自己肯定感をむしばみます。
でも明るい人たちは、競争相手を「他人」ではなく「昨日の自分」に設定しています。
- 昨日は5分しか読めなかったけど、今日は10分読めた
- 昨日は言い返したけど、今日は笑顔で流せた
このような『自分との勝負』が、自信を生み、穏やかな明るさを育ててくれるのです。
3. 「自分に話しかける言葉」を選ぶ
「どうせ無理だよ』、「また失敗する」
こんな言葉を、無意識のうちに自分に投げかけていませんか?
明るい人は、自分に向ける言葉をとても大切にします。
- 「やってみよう」
- 「大丈夫、今までだって何とかしてきた」
- 「まぁいっか」
こうした内なる声の選び方が、その人の気分と行動を決定づけます。
4. ネガティブは“感じきって手放す”
明るい人は「ポジティブに無理やり変換する」のではなく、「ネガティブを否定しない」ことも上手です。
- 落ち込むときはしっかり落ち込む
- 泣きたいときは泣く
- イライラしたら少し1人になる
そうやって感情を『感じきってから手放す』ことで、後に引きずらない強さを手にしています。
5. 小さな「達成」を積み重ねる
1日1つでも「やれた!」と思えることがあると、気分は驚くほど前向きになります。
- メールを1通返した
- 洗い物をすぐやった
- 5分間だけストレッチをした
こんな『小さな完了体験』が、自信と明るさを毎日育ててくれるのです。
マイケルの気づきコーナー
明るさは、考え方のチューニングでつくられる。
今日の言葉・視点・態度は、自分で選べる。
だからこそ、明るい人は「意識して明るくあろう」としている。
第5章 「意欲」がすべての源泉になる
明るさとは、単なる“性格”の話ではありません。
本書を読み進めるうちに、はっきりと見えてくるのが
「明るい人」は、意欲のエネルギーに満ちている人
ということなんです。
ここでいう“意欲”とは、
- 何かに挑戦したいと思う気持ち
- もう少し良くなりたいという願望
- 生きることへの関心
そのものなんです。
和田さんはこの「意欲こそが、人生全体を明るく照らす最大の燃料」だと語ります。
意欲があると、落ち込んでも立ち上がれる
意欲がある人は、壁にぶつかっても諦めません。
なぜなら、「その先に楽しみや意味を感じているから」です。
たとえば、
- 「もう一度挑戦したい」
- 「次こそやり遂げたい」
- 「あの人に喜んでもらいたい」
こうした前向きなエネルギーは、失敗や批判を飲み込み、前に進む原動力になります。
一方で意欲が枯れると、人は行動することすら面倒になります。
「どうせうまくいかない」
「もう頑張らなくていいや」
こうした無気力が、心を暗く閉ざしてしまうのです。
意欲は“気合”ではなく“習慣”で育てる
和田さんは、「意欲を出すには根性はいらない」と語ります。
必要なのは、「小さな楽しみ」や「達成感」を積み重ねていくこと。
たとえば
- 朝、好きな音楽をかける
- 帰宅後、5分間の読書で満足感を得る
- 夜、今日の“できたこと”をメモする
こうした小さな「よかった」を意識するだけで、意欲は自然と回復していきます。
意欲とは、エンジンではなく充電池。
自分で日々、充電することができるのです。
「楽しいから意欲が出る」ではなく…
「意欲があるから楽しくなる」
実は順番が逆なのだと、本書では繰り返し語られています。
やる気がないときでも、とりあえず手を動かしてみる。
体を動かすと、脳も“やる気モード”に切り替わる。
だからこそ、気分が乗らないときほど、
- 体を動かす
- 声に出して自分を励ます
- 小さな「できた」を見つける
この3つが、明るさと意欲を呼び戻す最短ルートなのです。
マイケルの気づきコーナー
意欲は、才能じゃない。
毎日の“ちょっとした満足”が、明日を照らしてくれる。
やる気は、後からついてくる。
第6章 明るさは人間関係を変える力になる
明るさの力は、ただ自分の気分が良くなるだけではありません。
周囲との人間関係にも大きな影響を与えます。
人は、ポジティブな感情や表情を持つ相手に対して、無意識に心を開きます。
笑顔で接してくれる人、話しかけやすい雰囲気のある人には、自然と好感を抱きますよね。
和田さんは、これを「感情の伝染」と説明します。
感情は伝染する
例えば、職場でひとりが不機嫌だと、周りもピリついてしまう。
逆に、誰かが明るく笑っていれば、その場の空気がふっと和らぐこともある。
このように、人間の感情は「ミラーニューロン」という脳の仕組みによって、他人に写り込んでいくのです。
つまり、自分が明るくいることは、それ自体が“他人へのプレゼント”になるということ。
明るさは「安心感」を生む
特に人間関係において重要なのは、「この人といると安心する」と感じてもらうことです。
明るい人は、声のトーン・表情・言葉選びが柔らかく、相手を責めることが少ない。
だからこそ、自然と周囲に人が集まってくるのです。
これは決して「八方美人」や「愛想笑い」とは違います。
本当の明るさとは
「自分がご機嫌でいることによって、相手を安心させられる力」
マイケルの気づきコーナー
明るさは“社交スキル”じゃない。
それは「人に与える安心感」の総量だ。
僕たちは、今日も誰かの心に光を灯せる。
第7章 暗さを責めない生き方
本書の魅力のひとつは、「明るさを推奨する本」でありながら、「暗い気持ちになることも当然」と優しく受け止めてくれる点です。
世の中の自己啓発書には、時に「ポジティブになれ」「前を向け」といった無理強いが見られます。
しかし和田さんは、「ネガティブになるのは人間として当たり前」と言います。
ネガティブは“弱さ”ではない
- 落ち込む日がある
- 愚痴りたくなるときもある
- 何もしたくない朝だってある
それらを「ダメなこと」と切り捨てるのではなく
「心が一時的に疲れているだけ」と捉えること。
そう考えるだけで、自分を責めずにすみます。
気分は天気と同じ。変わっていくもの
明るさは、ずっと晴れ続ける空のようなものではありません。
時には曇りや雨の日もあって当然。
和田さんは、「気分は天気のようなもの」と繰り返します。
つまり、「今は曇ってるな」と客観的に見るだけで、その感情に飲まれずにすむのです。
マイケルの気づきコーナー
明るくなるために、まず「暗さ」を受け入れよう。
自分に厳しい人ほど、優しさを自分に向けてあげてほしい。
その一歩が、心のリズムを整えてくれる。
第8章 和田秀樹さんの臨床現場からのリアルな声
和田秀樹さんは、精神科医として40年以上、数万人の心と向き合ってきました。
本章では、その豊富な臨床経験の中で見えてきた“明るさ”の真実が語られます。
明るくなると、回復が早くなる
驚くべきことに、うつ病の患者さんの中でも、「意欲」や「好奇心」が少しでも残っている人は、回復が早い傾向にあるそうです。
「この本、読んでみようかな」
「少し散歩してみようかな」
そう思えるだけで、心の再起動が始まるのです。
高齢者ほど「明るさ」が鍵になる
和田さんは現在、高齢者の認知症ケアにも深く関わっています。
その中で強く感じているのが、「明るい雰囲気の人ほど、老化に抵抗する力が強い」ということ。
- 人と関わる意欲
- 前向きに笑う習慣
- 小さな幸せを感じる能力
これらが、心だけでなく脳の健康にも直結しているのです。
マイケルの気づきコーナー
明るさは、回復力だ。
心が傷ついても、もう一度立ち上がる力。
それは、誰もが持てる“内なるエネルギー”。
第9章 1日10分でできる明るくなる習慣
ここまで読んで、「明るくなるには努力が必要そうだな」と感じたかもしれません。
でも安心してください、和田さんは、「1日10分でいい」と言います。
明るさは、小さな習慣の積み重ねで身につきます。
本章では、1日の流れに取り入れられる「3つの明るくなる習慣」が紹介されています。
① 朝の3分「口角上げトレーニング」
鏡の前で、無理やりでも笑顔をつくってみる。
最初は気恥ずかしくても、3日もすれば慣れてきます。
- 口角を意識して上げる
- 軽く目尻を下げて“微笑む”感覚をつかむ
これだけで、朝の自分が整ってくるのです。
② 昼の3分「立ち上がって深呼吸」
仕事の合間に、席を立ち、姿勢を正し、深呼吸を3回。
たったそれだけで、頭のモヤモヤがリセットされます。
感情が凝り固まったときは、「体からほぐす」が鉄則です。
③ 夜の4分「できたことメモ」
寝る前に、「今日できたことを3つ書く」だけ。
- ゴミ出しをした
- 無事に出勤できた
- 友人にLINEを返した
どんな些細なことでもOK。
『できた感覚』が、明日の自信につながっていきます。
マイケルの気づきコーナー
習慣は性格を変える。
明るくなるのは、毎日のちょっとした“選択”の積み重ね。
今日もひとつ、自分を整える習慣を。
第10章 明るい人生を生きるために、僕たちができること
ここまで読んできて、「明るさ」はもう特別なものではないと感じていただけたかもしれません。
才能でも性格でもなく、思考と習慣の選択によって、誰もが育てていける力なのです。
明るさは、自分にも他人にも“効く”
明るくなることで、
- 自分の気分が軽くなる
- 人間関係がよくなる
- 周囲に安心感を与えられる
- 心と体が健康になっていく
そんなふうに、明るさは“人生の土台”を強くしてくれます。
自分を照らせる人は、誰かの光にもなれる
これは僕の実感でもありますが、落ち込んでいる人の隣に「明るい人」がいるだけで、その場の空気が変わるんです。
言葉より、表情。
正論より、共感。
「大丈夫だよ」の一言よりも、「ニコッと笑ってる姿」に救われることだってあります。
最後に、マイケルからの提案
明るい人になることは、完璧を目指すことじゃない。
うまくいかない日もある。落ち込む日だってある。
それでも、少しだけ笑ってみる。
「なんとかなる」とつぶやいてみる。
昨日よりほんの少し、自分を大切にしてみる。
そんな1日1日の積み重ねが、人生を明るい方へと導いていくのです。
マイケルの気づきコーナー
明るく生きるとは、今日という日に希望を持つこと。
そして、自分の在り方が誰かの光になると信じること。
僕も、皆さんも、明るい人になっていける。
まとめ
ここまで読んでくださって、ありがとうございました。
『明るい人の科学』は
- 「笑うこと」
- 「気にしすぎないこと」
- 「ちょっとした達成を感じること」
そんな、誰でも今日からできる習慣が、人生を変える力を持っていると教えてくれました。
大事なのは
“完璧にポジティブになること”ではなく
「明るい方を少しでも選ぼうとする意志」そのもの。
もし今、何かにつまずいていたり、自信を失っていたとしても。
この本があなたの心を少しでも軽くしてくれたら、それがきっと“明るさ”の始まりです。
明日もまた、少しだけ笑っていきましょう。
📚 書評日記シリーズ|人生に効く本だけ、集めました
読書は、知識だけじゃなく“生き方”も整えてくれる。
このシリーズでは、僕自身が読んで心動かされた本、明日からの行動が変わった本だけを、厳選して紹介しています。
今の気分に合いそうな一冊があれば、ぜひ読んでみてください👇
- #1『世界の一流は「休日」に何をしているのか』| 休むとは、整えること
- #2『人生をガラリと変える「帰宅後ルーティン」』| 疲れた夜に未来を仕込め
- #3『明るい人の科学』| “明るさ”は才能じゃない ←今回の記事
📖あなたの明日を変える1冊が、きっとここにある📖