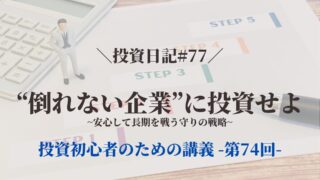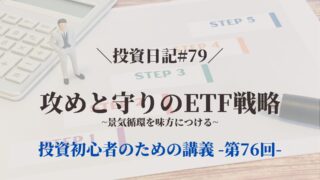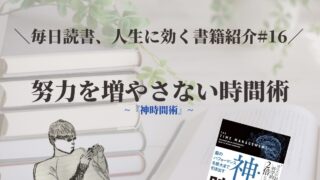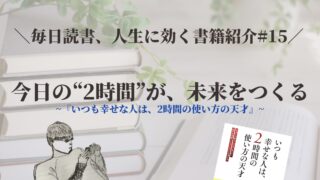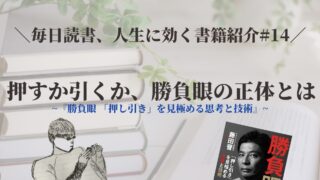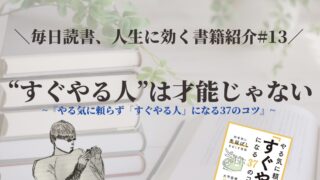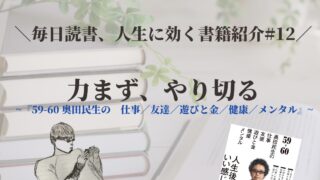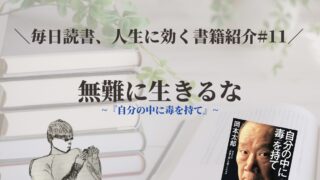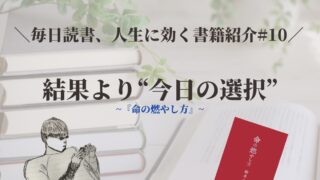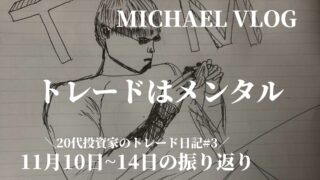投資初心者のための講義 ~ 第75回 ~『ディフェンシブ株ETF入門|不況に強い業種へ投資する戦略』【投資日記#78】
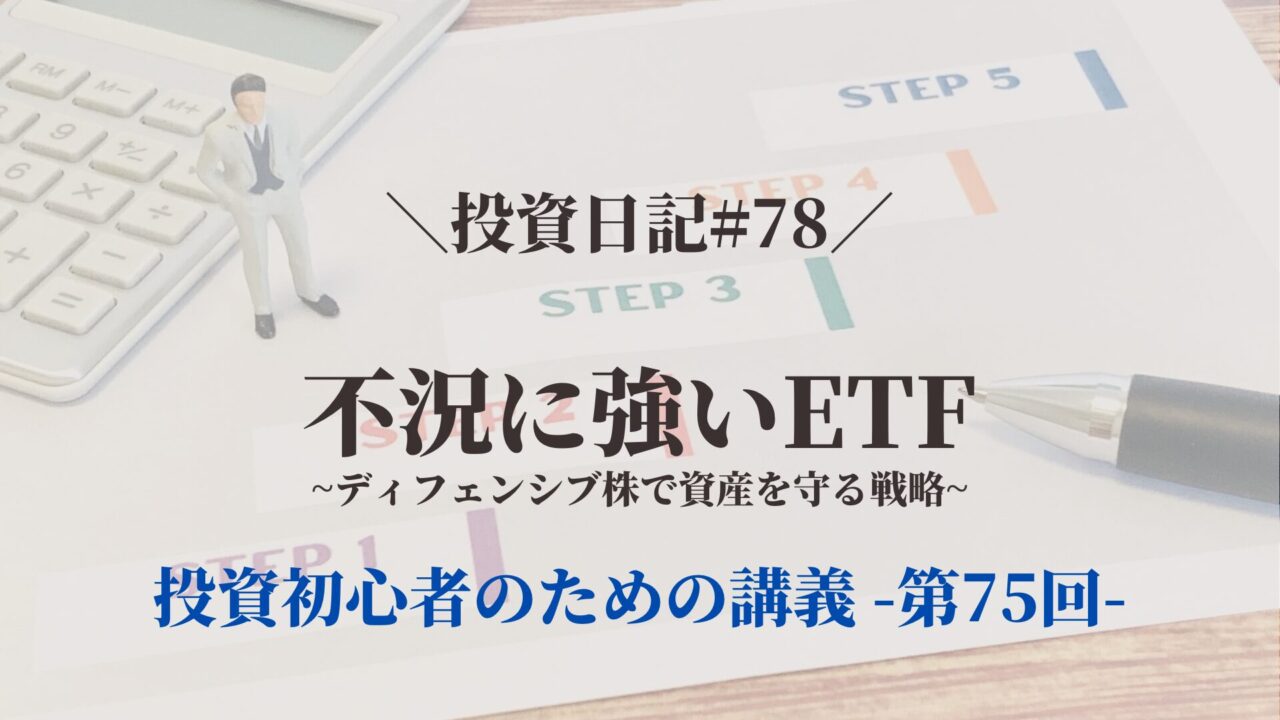
📘投資初心者のための講義シリーズ
このシリーズでは、投資をゼロから学びたい方に向けて「かんたん・やさしく・本質的」にお届けしています。
~未来を変える一歩を、今日から一緒に踏み出しましょう~
目次
暴落に備える守りの戦略
こんにちは!
どうも、マイケルです!
投資の世界に足を踏み入れると、最初に感じる不安は「暴落に耐えられるか」です。
- リーマンショック
- コロナショック
- インフレによる急落
こうした局面では、多くの投資家が資産を大きく減らし、市場から退場してしまいました。
しかし一方で、暴落時でも比較的安定していた企業群があります。
- 「人は不況になっても電気を使い続ける」
- 「病気になれば治療を受ける」
- 「日用品は買わざるを得ない」
この“生活に欠かせない”分野こそがディフェンシブ株です。
今回は、その守りの力を活かす「ディフェンシブ株ETF」について、徹底的に掘り下げていきます。
ディフェンシブ株とは何か
ディフェンシブ株は、景気循環に左右されにくい収益構造を持つ企業の株を指します。
- 生活必需品(Consumer Staples)
食料品・飲料・家庭用品を扱う企業。たとえ不況でも必ず消費されます。
→ 例:コカ・コーラ、プロクター&ギャンブル(P&G)、ウォルマート - ヘルスケア(Healthcare)
医薬品や医療機器メーカー。医療は人間の基本ニーズであり、需要が途切れません。
→ 例:ジョンソン&ジョンソン、ファイザー、ユナイテッドヘルス - 公益事業(Utilities)
電気・ガス・水道を供給する企業。生活に不可欠であり、景気動向に関わらず利用されます。
→ 例:デューク・エナジー、ネクステラ・エナジー
この3つのセクターは、いずれも「社会に必要不可欠」という共通点があり、安定的なキャッシュフローを確保しています。
そのため株価の変動が緩やかで、暴落時の下げ幅が小さくなる傾向があるのです。
ディフェンシブ株ETFの魅力
ディフェンシブ株ETFには、投資家が安心して持てるいくつかの強みがあります。
- 下落耐性の高さ
景気後退時に株価が下がりにくいという特徴があります。投資家が「避難先」として資金を移すことも多く、結果的にディフェンシブ株の価格は相対的に安定します。 - 安定した配当収入
成長株のような爆発的な株価上昇は期待できませんが、ディフェンシブ株は利益が安定している分、定期的に配当を出す傾向があります。ETFとして投資すれば、分散しながらその恩恵を受けられます。 - 心理的安心感
株価が急落する局面でも、ディフェンシブ株ETFを持っていることで「全資産が大幅に減るリスク」を抑えられます。精神的に落ち着いて投資を継続できることは、実はリターン以上に大きな価値です。
代表的なディフェンシブ株ETF
ここで米国市場で代表的なETFを紹介します。
- XLP(生活必需品セレクトセクターSPDR)
コカコーラやP&Gなどを含み、日用品や食品分野に特化。 - XLV(ヘルスケアセレクトセクターSPDR)
医薬品・保険・医療機器の企業に分散投資。景気後退局面で特に強みを発揮。 - XLU(公益事業セレクトセクターSPDR)
電力やガスを供給する企業群に投資。配当利回りが比較的高く、インカム投資家に人気。
また、日本の証券会社を通じて購入できる「セクター連動投資信託」もあるため、少額から積立投資することも可能です。
過去パフォーマンスの傾向
ディフェンシブ株ETFの強みは、過去の暴落時にハッキリと表れています。
- リーマンショック(2008年)
S&P500は約−37%下落しましたが、生活必需品ETFは約−15%の下落にとどまりました。 - コロナショック(2020年)
短期的に市場全体は急落しましたが、ヘルスケア株はワクチン需要の高まりで比較的早く回復しました。 - インフレ局面(2022年)
成長株が大幅に下落する一方で、公益事業株は安定したリターンを維持しました。
このように「大きく勝つことはないが、大きく負けない」ことが最大の魅力です。
長期的に資産を積み上げる上で、この“守りの安定性”は見逃せません。
実践アドバイス
ディフェンシブ株ETFは「守りの投資」として非常に有効ですが、使い方を誤ると「安定しているけど全然資産が増えない」といった状態にもなりかねません。
初心者が実践する際のポイントを、より深く見ていきましょう。
- ポートフォリオの保険として組み込む
- 全資産の10〜20%をディフェンシブ株ETFに配分するのがおすすめです。
- 例えば、S&P500インデックス80%+ディフェンシブETF20%といった組み合わせにすれば、暴落時の下落を緩和できます。
- 実際に「クッション資産」を入れている人ほど、暴落相場でも冷静に積立を続けられる傾向があります。
- 景気サイクルに応じて柔軟に調整する
- 景気拡大局面ではグロース株ETFやクオリティ株ETFの比率を高め、景気後退が見えてきたらディフェンシブの比率を上げる、といった戦略も有効です。
- ただし「タイミング投資」を狙いすぎるのは危険なので、基本は「ベースとして持つ」意識を大事にしましょう。
- 配当を再投資する習慣を持つ
- ディフェンシブ株ETFは安定した配当が魅力です。
- 例えばXLPの利回りは2%前後と地味に見えますが、長期的に再投資を繰り返すと複利効果が効き、資産の成長に貢献します。
- 配当を「使う」のではなく「再投資する」という仕組みを作ることで、守りの資産がじわじわと攻めにも転じていきます。
- 攻めと守りのバランスを可視化する
- ディフェンシブETFを組み入れると「守りが強すぎて物足りない」と感じることがあります。
- そのため、グロースや高配当ETFとの組み合わせを定期的にチェックして、自分の資産配分が「攻守のバランス」を保っているか確認しましょう。
- バランスを可視化して管理することで、ブレない投資を継続できます。
まとめ
ディフェンシブ株ETFは、投資における「盾」のような存在です。
- 景気後退局面でも大きな下落を避けられる
- 安定した配当で心理的な安心感を持てる
- 長期投資で「やめずに続ける力」を支えてくれる
この3つが大きなメリットです。
派手な成長はないかもしれませんが、資産形成で一番重要なのは「長期的に市場に居続けること」です。
そのためには、攻めの資産だけではなく守りの資産を持つことが欠かせません。
ディフェンシブ株ETFは「リターンを最大化する投資」ではなく「リスクを最小化して投資を続けるための仕組み」です。
投資初心者が安心して長期投資を続けるために、必ず検討すべき存在と言えるでしょう。
次回予告
『セクター別ETFの使い方応用編|攻めと守りを自在に組み合わせる戦略』
ディフェンシブ株ETFを学んだことで、「守りの資産」の重要性が理解できたはずです。
しかし、実際の投資では守り一辺倒では資産は大きく増えません。
かといって攻めすぎれば暴落に巻き込まれて退場してしまうリスクがあります。
では、どうすれば良いのか?
答えは「攻めと守りをバランスよく組み合わせる」ことです。
次回の投資講義は
『セクター別ETFの使い方応用編|攻めと守りを自在に組み合わせる戦略』
- ディフェンシブETFをどのくらい持てば安心できるのか?
- グロース株ETFとクオリティ株ETFはどう位置づけるべきか?
- 景気サイクルに合わせてポートフォリオを調整する方法とは?
こうした疑問に答えながら、ETFを使った応用的な投資戦略をわかりやすく解説していきます。
📚 投資初心者のための講義シリーズ
初心者でも一から学べる「投資講義」シリーズを順番に読みたい方はこちらからどうぞ👇
- 【第1回】NISAってなに?
- 【第2回】投資信託ってなに?
- 【第3回】インデックス投資ってなに?
- 【第4回】S&P500と全世界株式の違い
- 【第5回】ドルコスト平均法とは?
- 【第6回】NISAはいくら投資すべきか?
- 【第7回】銘柄選びの考え方
- 【第8回】個別株・ETF・投資信託の違いとは?
- 【第9回】インデックス型 vs アクティブ型
- 【第10回】分散投資ってなに?
- 【第11回】リスクとリターンの関係
- 【第12回】長期投資はなぜ最強か?
- 【第13回】習慣としての投資
- 【第14回】積立額の正解とは?
- 【第15回】出口戦略の基本
- 【第16回】資産の取り崩し戦略
- 【第17回】『ライフ資産』の築き方
- 【第18回】投資の『ゴール設定』
- 【第19回】年齢別の投資戦略
- 【第20回】リスク許容度の見極め方
- 【第21回】下落相場で買える人のメンタル設計
- 【第22回】株価は見るべきか?
- 【第23回】ニュースに惑わされない
- 【第24回】相場に振り回されない『継続力』
- 【第25回】やめたくなる日の処方箋
- 【第26回】感情に強くなる投資マインド
- 【第27回】暴落相場での冷静力
- 【第28回】回復相場での立ち回り方
- 【第29回】天井圏の見極め方
- 【第30回】下げ相場の入り口を見極める方法
- 【第31回】リバウンド相場の見極め方
- 【第32回】買い場を見極めるための思考法
- 【第33回】底値戦略の活かし方
- 【第34回】キャッシュポジションの極意
- 【第35回】資産配分の黄金比率
- 【第36回】リバランスの極意
- 【第37回】利益を伸ばすリバランス戦略
- 【第38回】成長投資枠でのリバランス活用法
- 【第39回】リバランスを自動化する方法
- 【第40回】複利の正体とは?
- 【第41回】長期投資と複利の関係
- 【第42回】長期投資を続けるための実践法
- 【第43回】心を整えて継続する力
- 【第44回】恐怖をチャンスに変える逆転思考
- 【第45回】投資を“生活習慣”にする方法
- 【第46回】不安と欲望に揺れない思考法
- 【第47回】情報断食のすすめ
- 【第48回】感情に振り回されない投資ノート
- 【第49回】数字に惑わされない視点
- 【第50回】投資が人生にもたらす副産物とは?
- 【第51回】投資が人生哲学に変わるとき
- 【第52回】人生設計と投資戦略
- 【第53回】支出管理と投資力
- 【第54回】生活防衛資金の考え方
- 【第55回】収入の柱を増やす考え方
- 【第56回】お金より大切な資産とは?
- 【第57回】投資を自動化する仕組み作り
- 【第58回】投資家の心を守る習慣
- 【第59回】投資における孤独との向き合い方
- 【第60回】情報の波に溺れない技術
- 【第61回】投資家の時間軸を広げる思考法
- 【第62回】ライフプランと投資戦略
- 【第63回】リスクに強い投資戦略
- 【第64回】資産配分を決める極意
- 【第65回】米国主要指数の違いを理解する
- 【第66回】米国株を始める第一歩
- 【第67回】NASDAQ100に投資する方法
- 【第68回】ダウ平均株価に投資する方法
- 【第69回】米国主要3指数の使い分け戦略
- 【第70回】セクターETF入門
- 【第71回】高配当ETF入門
- 【第72回】グロース株ETF入門
- 【第73回】バリュー株ETF入門
- 【第74回】クオリティ株ETF入門
- 【第75回】ディフェンシブ株ETF入門 ← 今回の記事
- 【第76回】セクター別ETFの使い方応用編【次回予告】
📌 各回、約2,000字でじっくり学べる内容になっています。
ブックマークして繰り返し読むのがおすすめです!