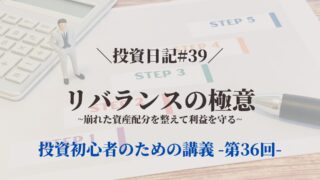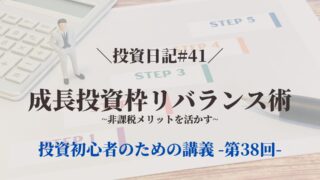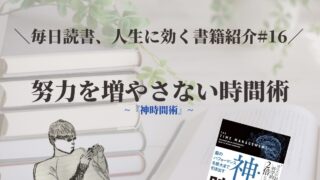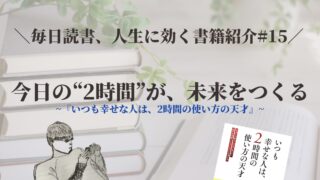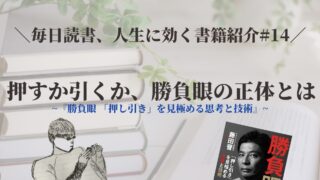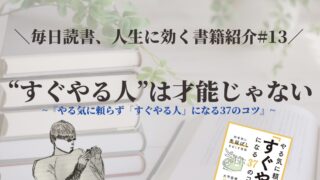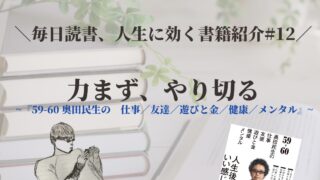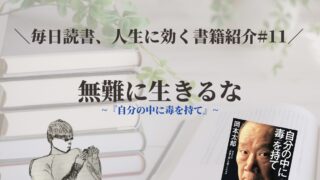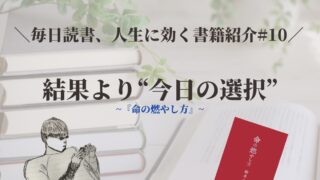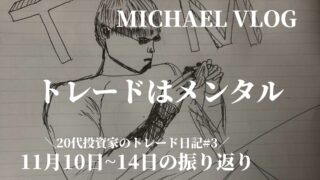投資初心者のための講義 ~ 第37回 ~『利益を伸ばすリバランス戦略|タイミングと頻度の極意』【投資日記#40】
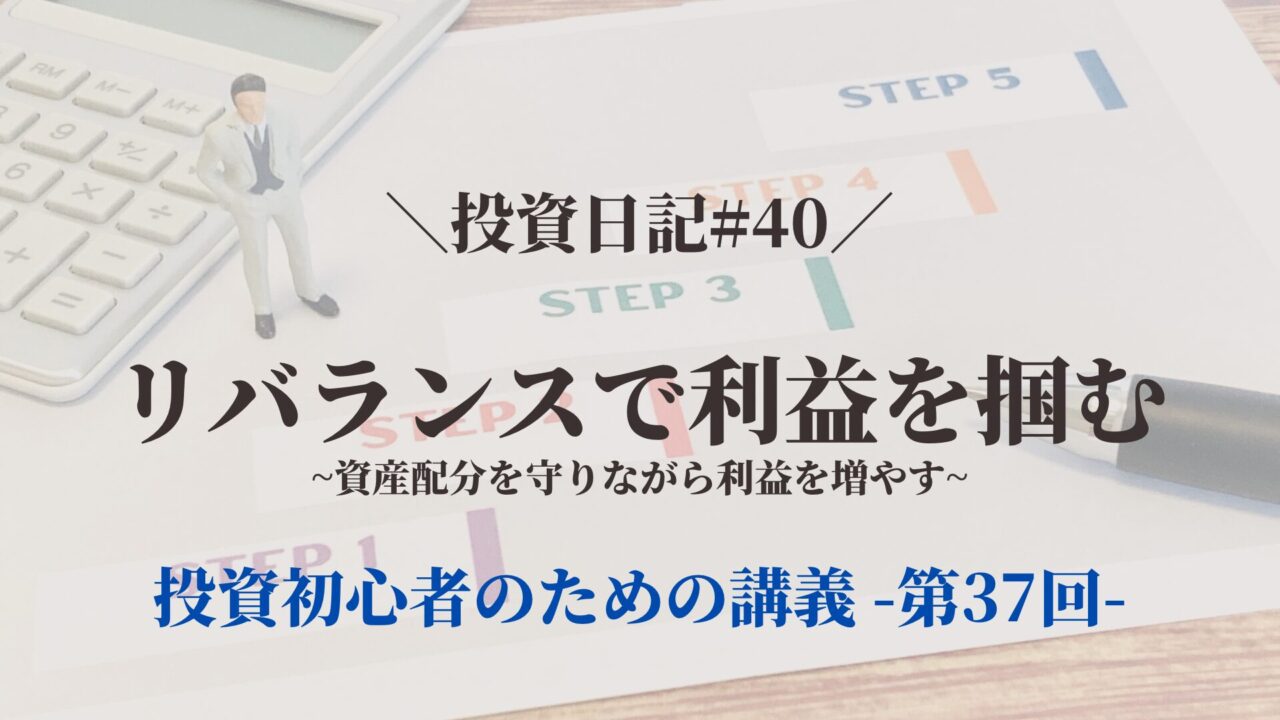
📘投資初心者のための講義シリーズ
このシリーズでは、投資をゼロから学びたい方に向けて「かんたん・やさしく・本質的」にお届けしています。
~未来を変える一歩を、今日から一緒に踏み出しましょう~
利益は待つだけじゃ増えない。
動かすことで、資産は加速する。
「リバランスって、資産配分を守るだけじゃないの?」
こんにちは!
どうも、マイケルです!
前回は「リバランスの極意」として、ポートフォリオを安定させるための守りの手法を解説しました。
資産配分を一定に保つことは、長期投資の安定性に直結します。
しかし、長期投資家の中には「守りのリバランス」だけでは物足りないと感じる人もいます。
特に、相場が大きく動いた局面では、「このチャンスを利益拡大に活かせないのか?」という発想が生まれるでしょう。
そこで今回は、リバランスを資産を守る盾から、利益を伸ばす剣へ変える方法。
すなわち、攻めのリバランス戦略を、タイミングと頻度の観点から深掘りします。
目次
守りから攻めへ──「攻めのリバランス」とは
通常、リバランスは「崩れた配分を元に戻す」だけの作業と捉えられます。
例えば
株式70%・債券30%のポートフォリオが、株価上昇で株式80%に偏った場合、株を売って債券を買い戻す。
これが守りのリバランスです。
しかし、攻めの視点ではもう一歩踏み込みます。
それは、値上がりした資産の一部を利確し、その資金を今後の成長が見込める資産に移すことです。
- 株が急騰したら一部利確し、まだ割安な株や新興国市場に回す
- 高リスク資産で得た利益を、安全資産や安定成長株に移して守りを固めつつ将来の種をまく
この考え方は「勝ち続ける馬に全てを賭ける」のではなく、「勝ち馬から利益を刈り取り、次の馬を育てる」戦略に近いです。
タイミングの極意
リバランスの最大の課題は「いつやるか」です。
攻めのリバランスにおいて有効なのは、定期的な見直しと相場変動時の機動対応の両立です。
(1) 定期型(年1〜2回)
- 例えば年末や年度末など、あらかじめ日程を決めて実施。
- メリット:感情に左右されない、ルール化しやすい。
- デメリット:相場急変時には機会損失が発生する可能性。
(2) 機動型(大幅変動時)
- 株式や特定アセットが±20%以上動いたら検討。
- 株価急騰時には利益確定→割安資産へシフト。
- 株価急落時には安全資産から株式へ資金移動して平均取得単価を下げる。
【実例】
- 株式60%・債券40%のポートフォリオが株式の急騰で70%になった場合、上昇分の10%を利確して債券や他の割安資産へ。
- 米国株が急落し、予定比率より15%低下した場合、安全資産を崩して米国株を買い増し。
頻度の見極め
攻めのリバランスは頻度を上げすぎると逆効果になります。
- 手数料やスプレッドコストが増える
- 頻繁な利確で複利効果が減少
- 相場の短期的なブレに振り回される
【ベストな頻度】
- 基本は年1〜2回の定期型+相場急変時の臨時対応。
- 新NISAの非課税枠であれば、課税リスクがないため臨時対応をやや増やしてもOK。
実践のコツ
攻めのリバランスを成功させるには、以下の3ステップが効果的です。
① 数字でルール化
- 「特定アセットが20%以上動いたら検討」
- 「株式比率が目標から±5%以上ずれたら実行」
② 小出し戦略
- 全額ではなく、上昇分・下落分の一部のみ動かす。
- 精神的負担を減らし、タイミング分散にもつながる。
③ 再投資先の厳選
- 利益移動先は必ず長期成長見込みのある資産に絞る。
- 流行だけで選ばず、ファンダメンタル(経済成長・企業収益)を重視。
まとめ
守りのリバランスは資産配分を守り、リスクを抑えるための必須戦略です。
一方、攻めのリバランスは利益を刈り取り、その資金を成長分野に再投資することで、長期リターンを底上げできます。
今回の要点は次の3つです。
- 定期型+機動型の組み合わせで、安定性と利益機会の両立を図る。
- 頻度は多すぎず、機会を逃さないルールを明文化する。
- 再投資先は成長が見込めるアセットに限定し、複利効果を維持する。
攻めのリバランスは、守りのリバランスを理解している人だけが使える“次のステージ”の戦略です。
焦らず、ルールを固めてから実践に移しましょう。
次回予告
成長投資枠でのリバランス活用法|非課税メリットを最大化する戦略
次回は「成長投資枠でのリバランス活用法」を解説します。
新NISAの成長投資枠は非課税で運用できるため、リバランス戦略の柔軟性が飛躍的に高まります。
どのアセットをどう動かせば、非課税メリットを最大限活かせるのか?
守りと攻めをバランスよく組み合わせた、成長投資枠専用のリバランス戦略を事例付きでお届けします。
守るだけじゃ終わらせない
攻めの一手で、資産は生き物のように成長する。
📚 投資初心者のための講義シリーズ
初心者でも一から学べる「投資講義」シリーズを順番に読みたい方はこちらからどうぞ👇
- 【第1回】NISAってなに?
- 【第2回】投資信託ってなに?
- 【第3回】インデックス投資ってなに?
- 【第4回】S&P500と全世界株式の違い
- 【第5回】ドルコスト平均法とは?
- 【第6回】NISAはいくら投資すべきか?
- 【第7回】銘柄選びの考え方
- 【第8回】個別株・ETF・投資信託の違いとは?
- 【第9回】インデックス型 vs アクティブ型
- 【第10回】分散投資ってなに?
- 【第11回】リスクとリターンの関係
- 【第12回】長期投資はなぜ最強か?
- 【第13回】習慣としての投資
- 【第14回】積立額の正解とは?
- 【第15回】出口戦略の基本
- 【第16回】資産の取り崩し戦略
- 【第17回】『ライフ資産』の築き方
- 【第18回】投資の『ゴール設定』
- 【第19回】年齢別の投資戦略
- 【第20回】リスク許容度の見極め方
- 【第21回】下落相場で買える人のメンタル設計
- 【第22回】株価は見るべきか?
- 【第23回】ニュースに惑わされない
- 【第24回】相場に振り回されない『継続力』
- 【第25回】やめたくなる日の処方箋
- 【第26回】感情に強くなる投資マインド
- 【第27回】暴落相場での冷静力
- 【第28回】回復相場での立ち回り方
- 【第29回】天井圏の見極め方
- 【第30回】下げ相場の入り口を見極める方法
- 【第31回】リバウンド相場の見極め方
- 【第32回】買い場を見極めるための思考法
- 【第33回】底値戦略の活かし方
- 【第34回】キャッシュポジションの極意
- 【第35回】資産配分の黄金比率
- 【第36回】リバランスの極意
- 【第37回】利益を伸ばすリバランス戦略 ← 今回の記事
- 【第38回】成長投資枠でのリバランス活用法【次回予告】
📌 各回、約2,000字でじっくり学べる内容になっています。
ブックマークして繰り返し読むのがおすすめです!