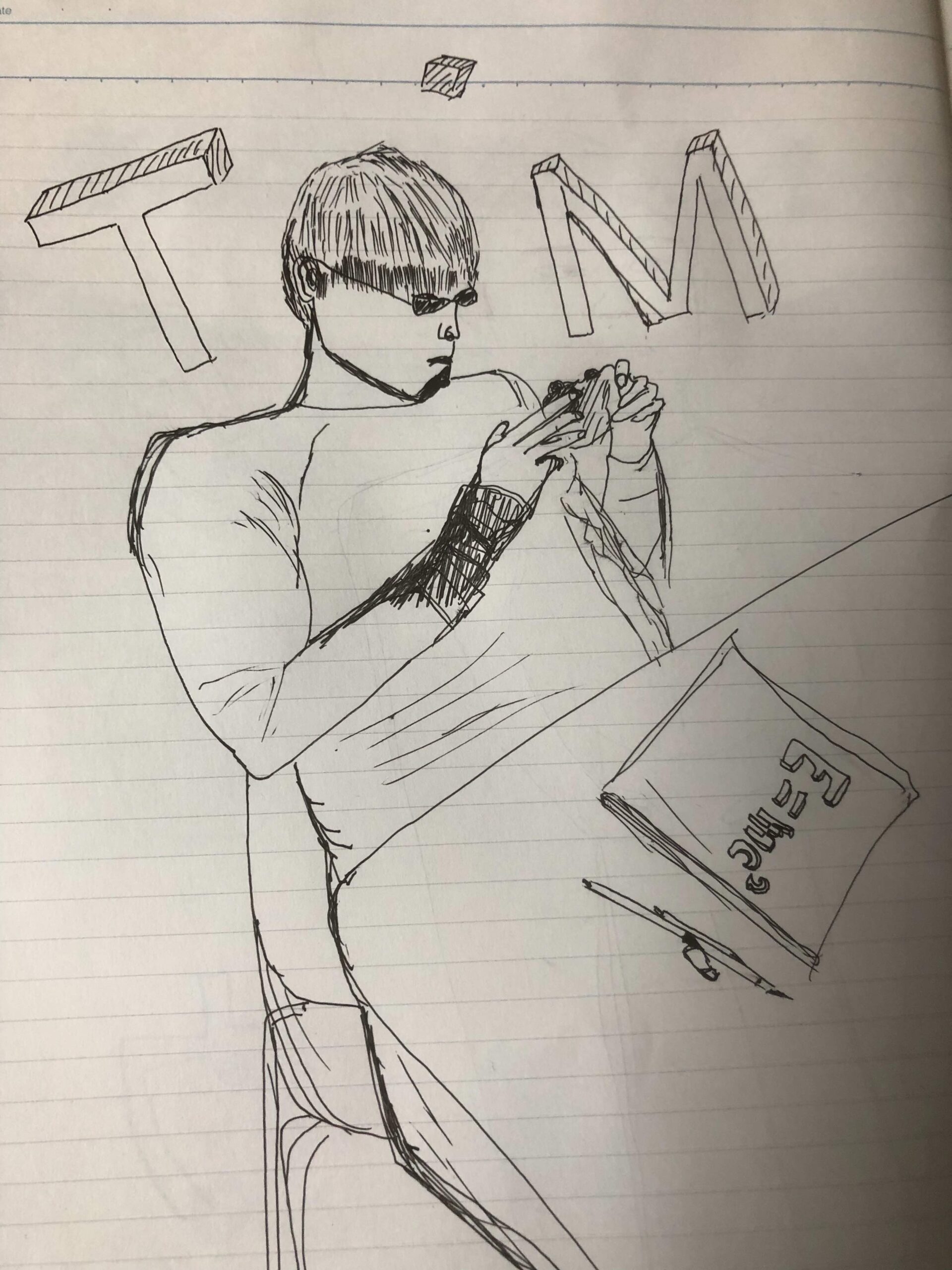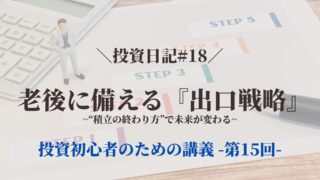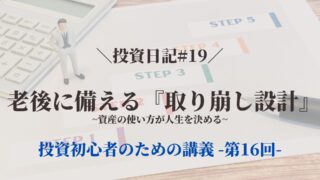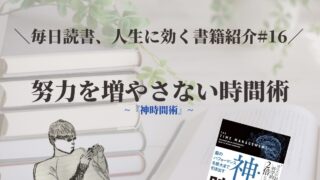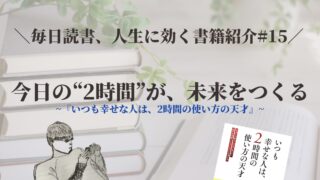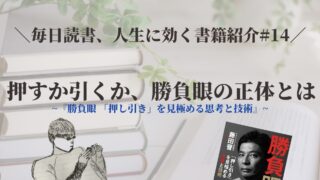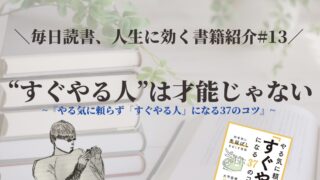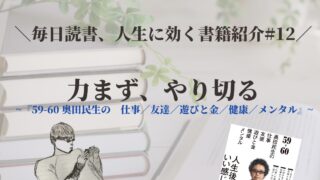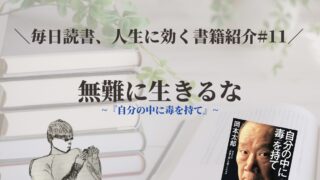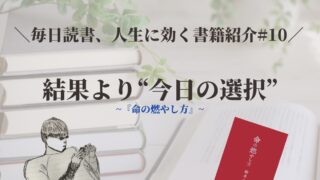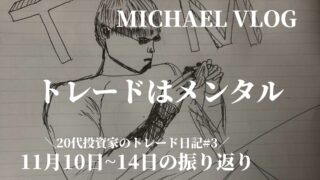#9|毎日読書、人生に効く書籍紹介『頭のいい人が話す前に考えていること』~「話し方」じゃなく「話す前」で、人生は変えられる~
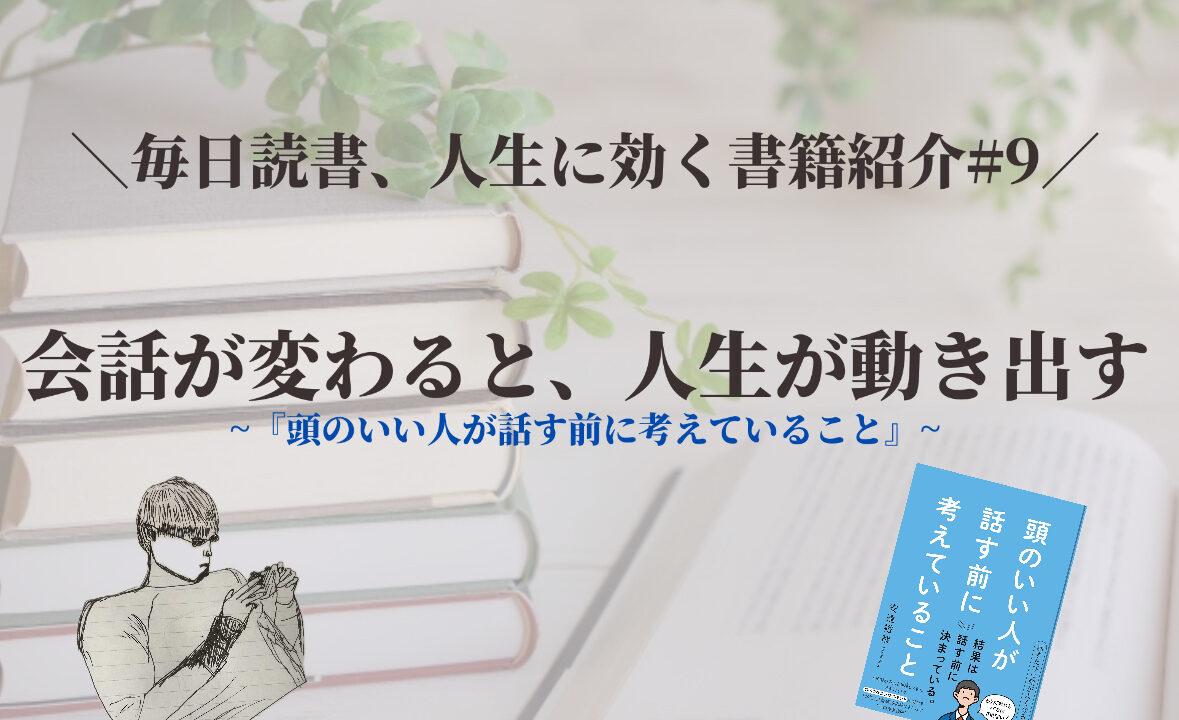
📘 この企画について
「毎日読書、人生に効く書籍紹介」は、ストイックに毎日一冊、本気で選んだ“人生に効く本”を紹介する連載企画です。
仕事・習慣・副業・自己成長に効く一冊を、実践的な視点で深掘りしています。
「話すこと」が変われば、人生が変わる
こんにちは!
どうも、マイケルです!
僕は普段、ブログやSNSで「伝えること」をテーマに日々発信を続けています。
- 文章を書く
- 音声で話す
- 人と対話する
どれも大切にしている活動ですが、実は長い間、自分の“話し方”にずっとモヤモヤを抱えていました。
「どうしたらもっと伝わるのか?」
「自分の言葉で人を動かすには、何が足りないのか?」
そんな問いの答えを探していたとき、出会ったのが本書『頭のいい人が話す前に考えていること』でした。
この本は、よくある“話し方のハウツー本”とはまるで違います。
話すスキルではなく、「話す前の思考設計」を徹底的に突き詰めた一冊なのです。
つまり
伝わるかどうかは「話す内容」ではなく
「話す前にどれだけ相手と目的を考え抜けたか」にかかっている。
これに気づけたことで、僕の発信は少しずつ変わっていきました。
この記事では、本書の要点と僕の学びを全10章で紹介していきます。
1章あたり約700字でテンポよくまとめているので、ぜひ最後までお付き合いください。
それでは、本題に入っていきましょう。
- 「話してるのに、なぜか伝わらない」とずっと悩んでいる人
- 会議やプレゼンで、毎回“手応えのなさ”を感じている人
- 人前で話すと、つい説明過多になってしまう人
- 話す力を磨きたいのに、テクニックだけでは変われなかった人
- 発信・対話・アウトプットを「武器」に変えたいすべての人
どれか1つでも当てはまるなら、
この本の中に、あなたの悩みを軽くするヒントがきっとあります。
(第9回の書籍はこちら)
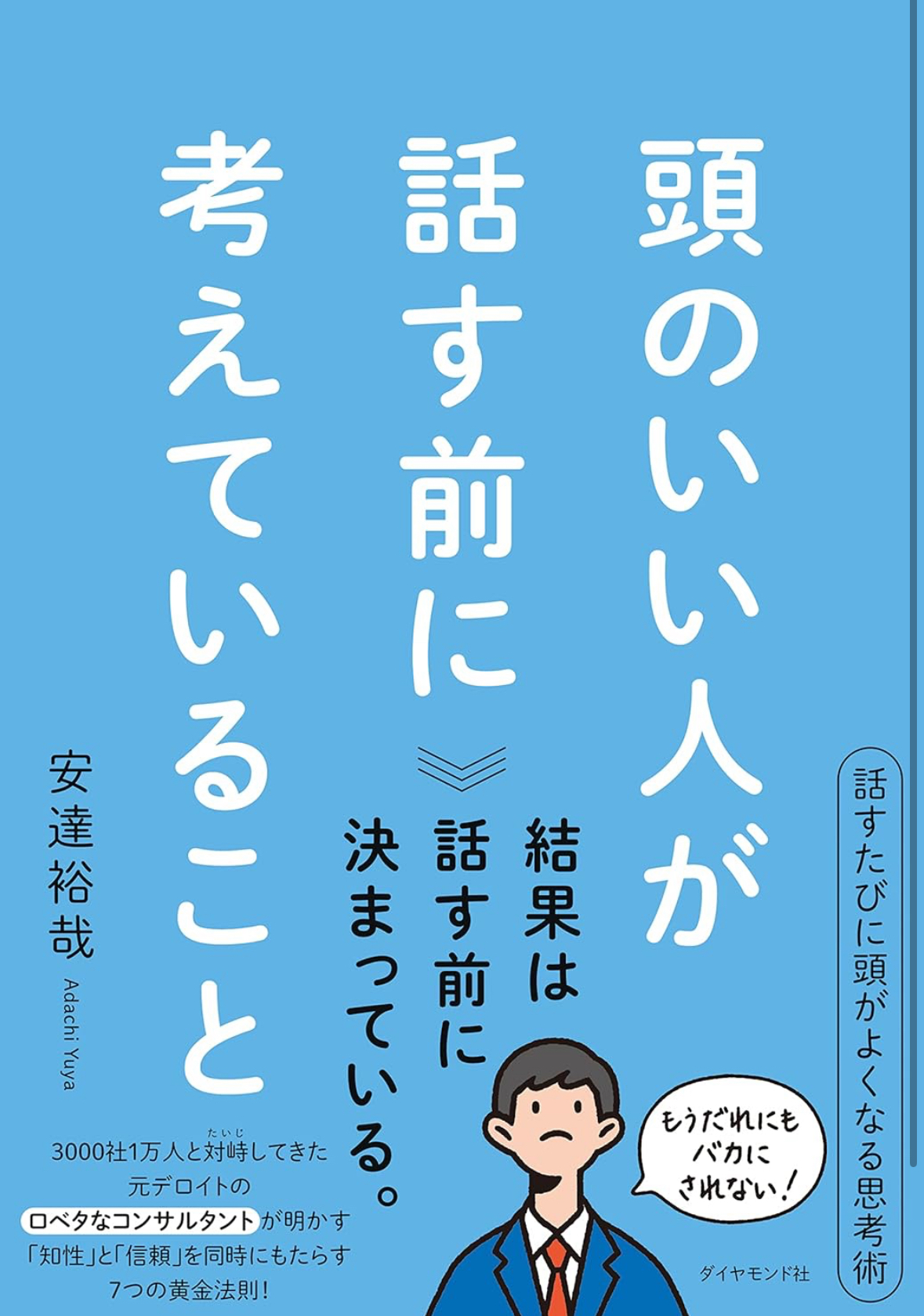
目次
第1章|話し方ではなく「話す前」に差が出る
多くの人は、話すことに不安や課題を感じると「どう話すか」に意識を向けます。
- 話し方のトーン
- 言葉のチョイス
- 論理展開の技術
たしかにそれらは重要です。
でも本書はその“前段階”にこそ、すべての本質があると教えてくれます。
安達裕哉さんは次のように語っています。
「本当に頭のいい人は、話す前に勝負がついている」
これは単なる比喩ではなく、実際に多くの成果を生んでいる人たちは、話し始める“前”に圧倒的な準備と思考を重ねているのです。
たとえば、
話す目的をはっきりさせる。
相手の理解レベルを推測する。
状況や関係性を考慮する。
そして何より、「何を言わないか」も決めておく。
こうした“話す前の設計”こそが、相手に届く言葉を生むのです。
僕自身も、以前は「話す技術」を磨けばうまくいくと思っていました。
でも、本書を読んでからは「話す前の時間こそが本番」だという感覚に変わりました。
言葉は、思考のアウトプットでしかありません。
- 出力より入力。
- 話すより、考えること。
この本は、「話すこと=思考のデザイン」という視点に気づかせてくれる、まさに“会話の哲学書”ともいえる一冊です。
第1章|マイケルの気づき
うまく話す必要はない。整えて話せば、それだけで届く。
第2章|「前提」がズレると、すべてが空回りする
話す力があるのに「なぜか伝わらない人」がいます。
逆に、言葉数が少なくても「スッと腹落ちする人」もいる。
この違いは、意外にも「話し方」ではなく、「前提の揃え方」にあります。
本書では、「話が伝わらない最大の理由は“前提のズレ”である」と明快に語られます。
たとえば、あなたが「この資料はコスト効率がいいです」と言ったとしましょう。
でも、相手が「今はスピード重視」と思っていたら、あなたの言葉はズレて聞こえます。
つまり
“話が伝わるかどうか”は、相手と「何を共有しているか」によって決まるのです。
安達さんは、話し始める前に「前提のすり合わせ」を習慣化することを強くすすめています。
- 相手が何を知っていて、何を知らないのか。
- どの視点から話を聞こうとしているのか。
それを見極める力が「伝わる会話」の根幹になるのです。
僕もこの考え方を取り入れてから、ブログや人との対話で「伝わらないモヤモヤ」が減りました。
- 「なぜそれを言うのか」
- 「相手はどう捉えるか」
このことを想像し、必要なら前提を補足してから本題に入る。
それだけで、コミュニケーションの質が驚くほど変わるんです。
話のうまさは、思いやりの設計。
聞き手の頭の中に橋をかける、その土台が「前提を揃えること」なのだと、本書は気づかせてくれます。
第2章|マイケルの気づき
話す前に、相手の「地図」を想像する。ズレはそこから生まれる。
第3章|削ることで、言葉に“芯”が宿る
「伝えたいことが多すぎて、逆に伝わらない」
そんな経験、きっと誰しもあるはずです。
本書では、その原因をズバリ「削る勇気の欠如」と喝破します。
つまり
“話す内容”ではなく、“話さない内容”を決めることが、話の精度を決めるのです。
安達さんは次のようにしっかりと語っています。
「頭のいい人は“何を言うか”ではなく、“何を言わないか”を決めている」
この言葉に、僕はハッとさせられました。
情報を盛り込めば盛り込むほど、説得力が出ると思っていた。
でも、実際には削ったときこそ言葉は研ぎ澄まされ、“芯”が浮き彫りになるのです。
たとえば、プレゼン資料。
全情報を載せたスライドより、要点を絞ったシンプルな構成のほうが、相手の集中力は保たれ、伝えたいメッセージがクリアになります。
これは文章も会話も同じ。
本書では「削る=捨てる」ではなく、「焦点を定める作業」として捉えることが重要だと説かれています。
僕は本書を読んで以降、話す前に「これは本当に必要か?」と何度も問い直すようになりました。
結果として、話す時間は短くなったのに、相手の理解度や納得感はむしろ増えました。
これはまさに“削る力”の効果です。
言葉のパワーは、情報量ではなく、明快さで決まる。
本書はその本質を、繰り返し教えてくれる一冊です。
第3章|マイケルの気づき
話しすぎは不安の裏返し。削る勇気が、言葉の強さになる。
第4章|「わかりやすさ」より「届くか」がすべて
「わかりやすく話すこと」が良いとされる時代。
でも本書は、そこに次のように、一石を投じています。
「わかりやすいかどうかより、“届くかどうか”が重要なのだ」
これはつまり
話し手が満足する「わかりやすさ」ではなく、
聞き手の中に“意味として届くかどうか”にこそ価値がある
ということです。
いくら論理的でも、相手の関心や理解レベルからズレていれば、その言葉は空を切るだけなのです。
安達さんは、「伝えること」と「理解させること」の違いを明確に区別します。
伝えただけでは意味がない。
相手の頭の中で再構築され、“自分ごと”として認識されて初めて、言葉は届いたことになる。
僕も発信を続ける中で、「話したのに伝わってない」と感じることがよくありました。
そのときはたいてい、「自分の基準で語っていた」とき。
本書を読んで以降、「相手の世界に届く言葉とは何か?」という視点を意識するようになりました。
わかりやすく話すことはスタートライン。
届かせるためには、相手の“心の受信機”に合わせて、言葉の周波数を調整することが必要なのです。
第4章|マイケルの気づき
「わかりやすさ」に満足するな。「届いたか」を見届けろ。
第5章|「構造」で語れ――主語・目的・結論を明確に
話が伝わらないとき、多くの人は「もっと説明しよう」としてしまいます。
しかし本書は、「構造がない話はいくら言葉を加えても伝わらない」と断言します。
話の構造とは、たとえば「主語」「目的」「結論」を明確にすることです。
誰の話なのか
何のための話なのか
そして最終的にどうしたいのか。
この3つを整理するだけで、話の理解度は大きく変わります。
本書では、「まず“目的”を明確にせよ」と強調されていました。
たとえば「何を伝えたいか?」よりも、「なぜそれを伝えたいのか?」のほうが、話の軸になります。
目的が明確であれば、話す内容は自然に絞られ、順序も決まっていくのです。
僕も日々の会話やブログ執筆で、「話の構造」を強く意識するようになりました。
起承転結ではなく、「なぜ・なに・どうする」の3軸。
これを整えておくだけで、相手の“理解スピード”が一段と上がるのを感じます。
構造化とは、聞き手への配慮でもあります。
「わかりやすく話す」の正体は、構造的に語る力なのです。
第5章|マイケルの気づき
話に“構造”がなければ、どんな熱量も空回りする。
第6章|「翻訳力」が、対話の精度を上げる
本書を通して特に印象的だったのが、「翻訳力」というキーワード。
これは、難しい言葉を易しく言い換える、という単なるテクニックではありません。
相手の立場や知識レベルを踏まえて“再構成する力”です。
たとえば、ビジネス用語をそのまま使えば、社内では通じるかもしれない。
でも、違う業界の人や初心者には届きません。
そういうとき、「たとえる力」「日常に引き寄せる力」が必要になるのです。
安達さんは、これを“対話の精度を上げる技術”と呼びます。
自分の言葉を、相手の文脈に合わせて翻訳することで、初めて「わかる」が生まれる。
僕はこの視点を、『投資日記』に応用しています。
専門用語は極力避け、読者の生活感覚に近い言葉を選ぶ。
中学生にも伝わるか?という視点で何度も書き直す。
それだけで読まれ方は大きく変わりました。
翻訳力は、知識の量ではなく、思いやりの表現。
相手の理解に寄り添うことで、言葉は初めて“届く言語”になるのです。
第6章|マイケルの気づき
翻訳とは、思いやりの再構築。相手の言語で語れ。
第7章|僕がこの本で実践した3つの変化
ここからは、僕が実際に本書を読んでから変わったことを3つ紹介します。
①「話す前に、目的と前提を整理する」
以前は“とりあえず話す”スタイルでしたが、今では「誰に何を伝えるか? 何を削るか?」を紙に書き出すようになりました。
②「構造を整えてから話し始める」
ブログや日々の会話で「起点→展開→結論」の順に整えてから話すようにしました。
読者の離脱率も大きく下がって、以前よりも最後までしっかりと読んでもらえるようになりました。
③「翻訳力を意識する」
難しい表現を、相手の生活や感覚に引き寄せて話す。
これにより、コミュニケーションが格段に深くなりました。
特に驚いたのは、「話す内容」は変えていないのに、「受け取られ方」が変わったこと。
まさに“話す前に勝負がついている”という実感です。
学んだことを実践し始めた途端、成果が現れる。
この本は、「行動を変える言葉」が詰まった一冊です。
第7章|マイケルの気づき
言葉を変えたら、相手の反応が変わった。つまり、世界が変わる予兆だ。
第8章|「話すこと」は、自分の思考そのものだった
本書を読み終えて感じた最大の気づきは、「話すという行為は、自分の思考の鏡だ」ということです。
つまり
話し方には、その人の“考え方の癖”がそのまま出る。
話がまとまらないのは、思考がまとまっていないから。
伝わらないのは、相手の立場に思考が及んでいないから。
安達さんは、話すことを「思考のアウトプット」と定義します。
そして、「話す前に考えること」こそが、思考の深度を決める。
この視点を持つと、話すことが“訓練”になります。
話すたびに、自分の思考の質が問われる。
雑に話せば、雑な思考が露呈する。
だからこそ、話す前に考える
そのプロセスが、自分自身を磨く行為になるのです。
僕もこの本に出会ってから、話す前に「何を整理すべきか」を問いかけるようになりました。
それだけで、対話の質も、日常の気づきも格段に変わりました。
話し方を学ぶ前に、「考え方」を鍛える。
この順番こそが、すべてを変える第一歩なのです。
第8章|マイケルの気づき
話し方を変えるたび、思考の濁りが少しずつ澄んでいく。
第9章|学びを定着させる読後アクション3選
この章では、本書の学びを現場で活かすための「3つの実践アクション」を紹介します。
① 「話す前に3つの問いを立てる」
「誰に? 何を? なぜ?」という問いを、話す前に1分で整理する。
これだけで伝わる力は劇的に変わります。
② 「毎日1アウトプットを構造化して書く」
ブログ・SNSの投稿でも、「目的→背景→メッセージ→補足」の流れを意識。
構造化の筋トレになります。
③ 「話す前に1回“削る”」
話す前に内容を1つ削ってみる。
その引き算が、言葉の強度と焦点を高めます。
本書は読みっぱなしではもったいない。
実践してこそ意味があります。
そして実践は、日常の“ちょっとした意識”から始められるのです。
考えて、使って、日々の対話で“変化の兆し”を感じてほしい。
それがこの本から僕が受け取ったメッセージです。
第9章|マイケルの気づき
学びは“読んだか”じゃない。“使ったか”で決まる。
第10章|会話が変わると、人生が変わる
本書を通して実感したのは、「会話は人生を変えるツール」だということ。
話す力が磨かれると、人との関係性が変わり、仕事も、信頼も、成果も変わっていきます。
しかもそれは、小手先のテクニックではなく、「話す前の思考力」から始まる。
本書はその“基礎体力”を鍛えてくれる一冊です。
僕も、本書を読んでからの数日で、人とのやりとりにおける“納得度”が明らかに上がりました。
- 言葉が届くと、相手が変わります。
- 相手が変わると、関係が変わります。
- 関係が変わると、人生が動き出す。
つまり
話す力とは「人生を設計する力」
この本は、会話を通じて人生を再構築するための、思考のツールキットなのです。
第10章|マイケルの気づき
話すことは、人生を再設計するための静かな革命だ。
おわりに|マイケルの気づき
「話す前に、勝負は決まっている」
本書を通して最も深く刺さった言葉です。
言葉は、発するその瞬間ではなく、その“前”にどれだけ思考を重ねたかで、すべてが決まる。
本書は「話し方」を学ぶ前に、「自分の頭の使い方」を整えてくれる。
だからこそ、話し方のハウツー本に疲れたすべての人に読んでほしいと、心から思います。
これからも僕は、「話す前に考える」という習慣を武器にしていきます。
最後まで、読んでくださってありがとうございました。
また次回の書評でお会いしましょう!
📚 書評日記シリーズ|人生に効く本だけ、集めました
読書は、知識だけじゃなく“生き方”も整えてくれる。
このシリーズでは、僕自身が読んで心動かされた本、明日からの行動が変わった本だけを、厳選して紹介しています。
今の気分に合いそうな一冊があれば、ぜひ読んでみてください👇
- #1『世界の一流は「休日」に何をしているのか』| 休むとは、整えること
- #2『人生をガラリと変える「帰宅後ルーティン」』| 疲れた夜に未来を仕込め
- #3『明るい人の科学』| “明るさ”は才能じゃない
- #4『STOIC 人生の教科書ストイシズム』| 外に振り回されない生き方
- #5『一流の人に学ぶ心の磨き方』|一流の人は、心を磨き続ける
- #6『悩まない人の考え方』|思考を整えれば、心は軽くなる
- #7『エッセンシャル思考』|本当に大事なことをやれ
- #8『愛とためらいの哲学』|愛するとは“覚悟”である
- #9『頭のいい人が話す前に考えていること』|会話が変わると、人生が動き出す← 今回の記事
📖あなたの明日を変える1冊が、きっとここにある📖